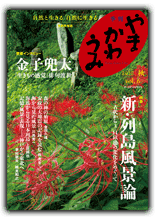|
フィルムメーカーズ | 個人映画のつくり方 |
| 金子 遊 編著 | ||
| A5判上製/カバー装 | ||
| 本文340頁 | ||
| 2011年4月発売 | ||
| 定価2,750円(本体2,500円) | ||
| ISBN:978-4-901592-63-5 | ||
他の書店で買う |
||
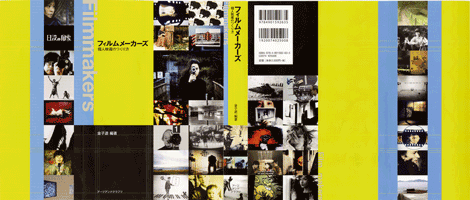
- 目次
- 第一章
「個人映画を学ぶ」海外の作家4名のテキストとインタビューの翻訳
- スタン・ブラッケージ「8つの質問」
- マヤ・デレン「個人映画と商業映画」「芸術形式としての映画」
- ジョナス・メカス「映画制作・批評・上映運動」
- クリス・マルケル「インタビュー(1968)」「インタビュー(1996)」
- 第二章
「個人映画をつくる」日本の個人・実験映画の作家たち 10 名のインタビュー
- 松本俊夫「実験映画の実践・私の初期と後期」
- 吉増剛造「詩的ヴィジョンとビデオカメラ」
- かわなかのぶひろ「日常を撮り続ける」
- 出光真子「ビデオアートとフェミニズム」
- 飯村隆彦「実験映画、概念芸術、ビデオアート」
- 伊藤高志「実験映画のトップランナー」
- 金井 勝「インディペンデント映画の先駆者」
- 原 將人「私の肉体が滅びるとき、私の映画もまた死す」
- 鈴木志郎康「極私的な世界を撮る」
- 石田尚志「ドローイング・アニメーションの魔術」
- 第三章
「個人映画を見る」14 作家の作品を専門家が紹介
- 越後谷卓司、高祖岩三郎、黒坂圭太、金惠信、岡村恵子、上野昂志、岩本憲児、クリストフ・シャルル、阪本裕文、西村智弘、正津勉、広瀬愛、水由章
- 書評・紹介
- この大部の労作が三部に構成されていることには、啓蒙的な意味が十分に表れている。第一章では個人映画・実験映画の歴史的な作家たち自身の発言を収め、第二章では、わが国の個人映画・実験映画の歴史に深く関わる作り手たちの発言を収める。そして第三章では、それらの作家たちの作品を批評・紹介するという構成である。
編者金子遊の繊細な企図がそこに感じられる。個人映画・実験映画と言っても、その呼称から実体が失われてすでに久しいからだ。金子の企図には、1960年代に絶頂にあった個人映画・実験映画の面影が、実は現在こそまさに蘇りつつあることへの熱い思いがある。かつては面倒な手続きが必要だったそれは、いま一切の手続きが省略されたデジタル映像とパソコン上に移行し、個人の「内的な欲求」の実現がとても簡便で融通の利くものとなっている。映画がもう一度、個人の手許に帰っているという認識が金子にはある。
第二章で作家たちから発せられる声の数々は、いまこの時代、膨大に撮られているだろう小さなビデオカメラによる個人的な映像の行方を見守っているようにも読めて、実に示唆的である。(一部抜粋)- (東京新聞・中日新聞 2011年5月8日)
- この大部の労作が三部に構成されていることには、啓蒙的な意味が十分に表れている。第一章では個人映画・実験映画の歴史的な作家たち自身の発言を収め、第二章では、わが国の個人映画・実験映画の歴史に深く関わる作り手たちの発言を収める。そして第三章では、それらの作家たちの作品を批評・紹介するという構成である。
- 著者紹介
- 金子 遊(かねこ・ゆう)
- 1974年、埼玉県生まれ。映像作家・脚本家。大学在学中に制作した16ミリ映画『わが埋葬』でメディアウェイブ・フェスティバル(ハンガリー)正式出品。2008年『ぬばたまの宇宙の闇に』で、奈良前衛映画祭NAC 賞(最優秀作品)受賞。劇場公開作品にドキュメンタリー映画『ベオグラード 1999』がある。
- ※ここに掲載する略歴は本書刊行時のものです。
- 関連書