���҈ꗗ�i50�����j
���s�F
-
�� �I���i�������E������j �吳3�N�i1914�j�A���䌧�։ꐶ�܂�B���a20�N�i1945�j�A�_�{�c�{�ّ�w���ƁB41�N�A�����w�w�|�w�������A54�N�A����w�������B�܂��A���a52�N���畽�����N�i1989�j�A�_�Ж{���������C���_�E���C��u�t�i���쎮�j���S���j�B���a55�N�A�Q�n�������q��w�����B���a62�N�A�M�O�����������͂����́B����17�N�A�����B�����Ȓ����E�Ғ��Ɂw���{�_�b�̊�b�I�����x�i���ԏ��[�j�A�w�j���x�i�����Ёj�A�w�_����n �ÓT���ߕҘZ �j���E�閽���߁x�i�_����n�Ҏ[��j�A�w��ΐ^���S�W �掵���x�i���Q���ޏ]������j�A�w�j���Ó`���̌����x�i�������s��j�A�w�j���S�]�߁x�w�u�Ì�E��v��ǂށx�i�E�����@�j�ȂǁB 
�m�V�Łn�j���\�u���쎮�j���v�{���ƌP�{�� �T�q�i�������E�䂤���j 1950�N�A���������܂�B�N�ljƁB�Óc�m��w�𑲋ƌ�A1973�N��NHK�ɓ��ǁB�A�i�E���T�[�Ƃ��āu�X�^�W�I102�v��u�j���[�X���C�h�v�Ŋ���B��N�ސE��A2010�N�A����𓊂��ē��{�ŏ��߂Ă̌y���N�NJق�ݗ��B�܂�2013�N�A�y����}���ْ��ɏA�C�B���݁A�ږ�E���_�ْ��B�����Ɂw�č��g�����v�x�i1992�N�A�����V���Њ��j�A�w�y���N�NJق����x�i2017�N�A�A�[�c�A���h�N���t�c���j������B 
�N�ǃX�e�b�v�A�b�v
�N�ǃ��[�N�V���b�v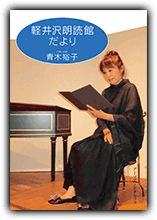
�y���N�NJق����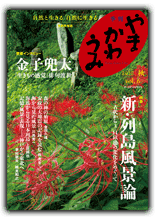
��� ���� ����
vol.6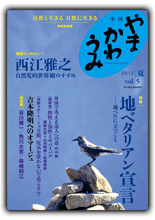
��� ���� ����
vol.5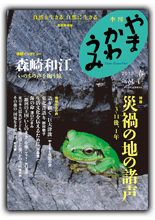
��� ���� ����
vol.4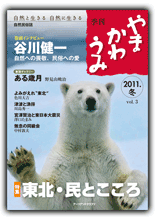
��� ���� ����
vol.3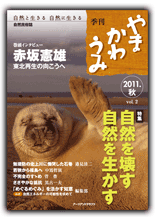
��� ���� ����
vol.2
��� ���� ����
vol.1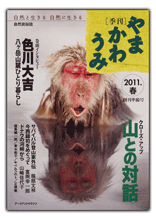
��� ���� ����
vol.0(�n���������j�H�R �x�i������܁E�����j 1930�N�A�������܂�B���啧���ȑ��B60�N�A�]�_�u���яG�Y�v�Łu�Q���v�V�l���w�܂���܁B90�N�A�w�l���̌��x�ňɓ������w��܁B96�N���s�́w�M���x�Ŗ�ԕ��|�܁A�����o�ŕ����܂���܁B�w�����̐l�ԁx�w���s�ƊL�k�x�w�ܐ̎v�z�x�w�m�ꂴ�鉊�\�]�`��������x�w�������Ƃ����l���x�w���b���x�ȂǑ����̒���������B 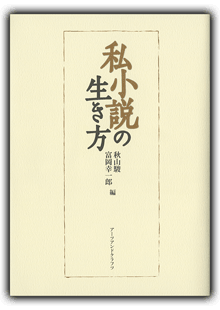
�������̐��������� �L���i����߁E�Ђ�͂�j 1953�N�L���s���܂�B���s��w�o�ϊw�����B���|�]�_�ƁA�ӂ���ܕ��w�يْ��A�m�[�g���_�����S���q��w���_�����B�����ɁA�w�E=���w�����@�|�X�g���_�j�Y����]�ɍR���āx�i���{�}���Z���^�[�A1999�N�j�A�w�ϗ��I�Ő����I�Ȕ�]�ց@���{�ߑ㕶�w�̔ᔻ�I�����x�iᩐ��ЁA2004�N�j�A�w���{�����@���Љ�E���E�E�V�c���x�w�q�u�Ɣ��Ӂ@���{�ߌ��㕶�w���猩�錻��Љ�x�i�䒃�̐����[�A2019�j�A�w���яG�Y�@�v�z�j�̂Ȃ��̔�]�x�w���Ɣj���Ƌ~�ςƁ\���{�ߑ㕶�w�ƕ����x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2024�N�j�ȂǑ����B ![���яG�Y�@�v�z�j�̂Ȃ��̔�]](../../img/book/shadow/book_155.gif)
���яG�Y�@�v�z�j�̂Ȃ��̔�]
���Ɣj���Ƌ~�ς�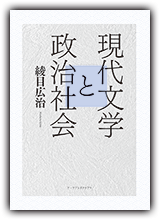
���㕶�w�Ɛ����Љ��� �`�l�i���炵�E�悵��ǁj ���a19�i1944�j�N�H�c������B�{�ЁE�V�������n�s�B
���{�@��{�@�w�����ƁA���{�@��{��w�@���w�����ȓ��{�j�w��U���m�ے��P�ʎ擾�����ފw�B���{�@��{���{�����������������B�����ȁi�̂������Ȋw�ȁj������������Nj��ȏ��������i�̂���C���ȏ��������j�B����16�N4����蕽��27�N3���܂Ś��{�@��{�_�������w�������B�܂��A��t���ȑ�w�A����w�A���m�ڑ�w�ȂǂŔ��u�t�߂�B![�]�]�Ǐ��@�w�̓��{�j�]�b](../../img/book/shadow/book_124.gif)
�]�]�Ǐ��@�w�̓��{�j�]�b�r�� �I�i���������E�����ށj 1940�N�A���Ɍ����܂�B�h�C�c���w�ҁE�G�b�Z�C�X�g�B���̃h�C�c���w�ȊO�ɂ��A�R�A����A���Ȃǂ��܂��܂ȃe�[�}�Ŏ��M������W�J���Ă���B��\��Ɂw慎h�̕��w�x�i�����ЁA�T�䏟��Y�܁j�A�w�C�R�̂������x�i�}�K�W���n�E�X�ق��A�u�k�ЃG�b�Z�C�܁j�A�w�Q�[�e�����́x�i�W�p�ЁA�K�����v�w�|�܁j�A�w���m��ʃI�g�J���\�҂܂��Ƃ̏ё��x�i�݂������[�j�A�w���n�F�l�Y�@��̓`�L�x�i���Y���[�A�ǔ����w�ܕ]�_�E�`�L�܁j�B�ɃQ�[�e�w�t�@�E�X�g�x�i�W�p�ЁA�����o�ŕ����܁j�ق��B 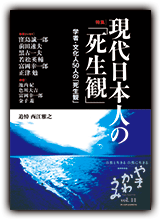
��� ���� ����
vol.11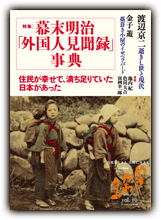
��� ���� ����
vol.10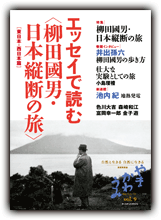
��� ���� ����
vol.9�s�� �^���i�����ނ�E�悹���j 1921�N�A��錧���܂�B������w���B
1979�N�A���ҕ]�_�w���ːߘ_�E�t�͓~�ɉ������āx�A81�N�w���ː߂̒Z�́x�i�Ƃ��ɑn�юЊ��j�\�A�Ǝ��̎��R�_������ɐ��������w�E�v�z�_�Ƃ��Ċe���ʂ���]������B�ߔN�͊e�n�𗷂��āA�_�������̖̂����E���y�ɁA�ʐ^��\���}�̂Ƃ��ăA�v���[�`�A91�N�ɂ͎ʔ��W�w�Ε��E���ق̔��x�i�A�[�c�A���h�N���t�c���j�\���Ă���B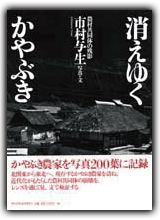
�����䂭����Ԃ��䓛 �����i���ÂE�������j 1947�N�A�����s���܂�A����c��w�����o�ϊw�����ƁB�S�Ȏ��T�E���j�G�����̕ҏW���o�āA�t���[�̕ҏW�ҁA�o�Ńv���f���[�T�[�A���C�^�[�B�咘�Ɂw���w���̂̌̋�������x�w���{�@���j�N�\�x�w���a�V�c������肫�x�w�V�c�ƑS�n�}�x�w�V�c�j�N�\�x�i�ȏ�A�͏o���[�V�Ёj�A�w���̎G�w���T�x�i���{���Əo�ŎЁj�A�����Ɂw�]�ˁE�����@����������x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�����ς炢��S�x�i�u�k�Ёj���B���{������̉����B 
�u�H�v�̂��Ƃ킴��m�鎖�T![�]�ˁE���� ���������](../../img/book/shadow/book_010.gif)
�]�ˁE���� ���������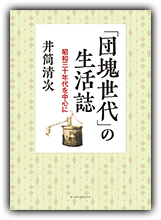
�u�c��v�̐������\���a�O�\�N��𒆐S������ �юi�i���܂ɂ��E���j 1902�N�A���s���w���܂�B���Ԋw�ҁA�����l�ފw�ҁA�o�R�ƁB���s�鍑��w���ƁB1939 �N�A�J�Q���E�̕��z�Ɋւ��鐶�Ԋw��������u���ݕ������_�v�ݏo���A���w���m�̊w�ʂ����^�B���́A�j�z���U���Ȃǂ̌�����i�ߓ��{�̗쒷�ތ����̑n�n�҂Ƃ��Ēm����B���s��w�����A��w�����C�B79�N�A�����M�͎�́B
�o�R�́A���s�k�R�A���{�A���v�X�A���N�����R�A�����勻����R���A�q�}�����ɂ���ԁB52�N�A���{�R�x��̃}�i�X���攭�����Ƃ��ăq�}�������B73�N�A��12����{�R�x���B85�N�A����1500�o�R��B���B1992�N�����B
��H�ɗ����R�Ɛl���F�� ��g�i���납��E���������j �@1925�N��t�����������i���E����s�j���܂�B������w���w�����j�w�ȑ��ƁB�����o�ϑ�w���_�����B���j�ƁB���O�j�E�����j�̒ҁB
�@�����Ȓ����Ɂw�������_�j�x�i��g���㕶�Ɂj�A�w���[���V�A�嗤�v���s�x�i�������Ɂj�A�w�k�����J�x�i����o�ʼn�j�A�w��{�@���j�̕��@�x�i�m���MC�V���j�A�w���a�ւ̃��N�C�G�������j�ŏI�сx�i��g���X�j�A�w�F���g����W�x�S�U���i�}�����[�j�A�w���k�̍Ĕ����x�i�͏o���[�V�Ёj�ȂǁB
��������j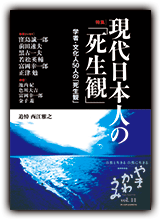
��� ���� ����
vol.11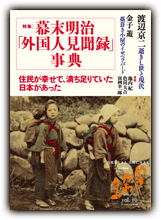
��� ���� ����
vol.10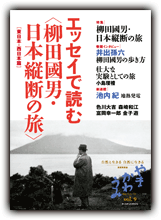
��� ���� ����
vol.9
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8
��������j�l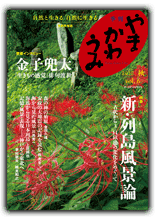
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6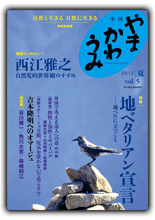
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5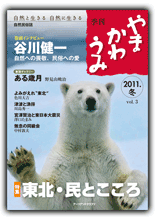
��� ���� ����
2011.�~�@vol.3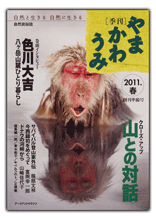
��� ���� ����
�n��������2011.�t�╣ �G�q�i����Ԃ��E�Ђ낱�j 1945�N�É������܂�B1968�N���{���q��w���w�������w�ȑ��ƁA1974�N����w�@���w�����ȓ��{���w��U�C�m�ے��C���B���{���q��w����A���a�w�@�Z����w��C�u�t�A����w���������o�āA1991�N���{���q��w�������A1996�N����w�����B���݁A�鐼���ۑ�w�q�������E���{���q��w���_�����B�����Ɂw�{�{�S���q�\�\�Ƒ��A�����A�����ăt�F�~�j�Y���x�i�˗я��[�A1996�N�j�A���Ҏ҂Ɂw�����������T�x�i�������o�ŁA2015�N�j�ȂǁB 
�t�F�~�j�Y���^�W�F���_�[��]�̌���
���㏗�����w��ǂ�
�R�W�����̌����c �����i�������E���j ���a�Q�N�i1927�j���܂�B���{�@��{��w�@���m�ے��I���B���{�@��{�w�����o�ē���w���_�����B�@���S���w�E�_���_�w��U�B����15�N�R�������B�����Ɂw�_���_�w�x�w�L�I�_�b�̐_�w�x�ȂǁB 
���w�̌������� ��Y�i�����́E���낤�j �吳�O�N�i����l�j�ꌎ����A�_�ސ쌧�ɐ��܂��B���a���N�ɚ��{�@��{�����Ȃ𑲋ƁB����ܔN�k�C���w�|��w�����B���O���N�ɂ͚��{�@��{���w�������ƂȂ�A����w�̓��{������������������������B�܋�N�l���ɓ���w���_�����B���̊ԁA���Ƃ̃{����w�q�������i���Z���N��Z�������㎵�Z�N�O���j�Ƃ��č��w�j����ѓ��{���|�����@���u�`�����B���a�O�Z�N�ɂ́u���{���|�j�̕��@�����v�ŕ��w���m�B���a�Z�Z�N�\�Ɏ����B
��v�����Ɂw���{���|�j�l�x�w���{���|�T�_�x�w���{���|�j�f�`�x�w���{���|�����@�x�w���|�w�j�̕��@�x�w�]�˔h���w�_�l�x�w���{���w�v���x�w�V���w�_�̓W�J�x�w���{���|�����j�x������B![�]�˔h���w�_�l](../../img/book/shadow/book_012.gif)
�]�˔h���w�_�l�C�� �O�i����́E�Ђ낵�j 1939�N�������܂�B����c��w���w�����ƁB�o�ŎЋΖ����o�āA���݁A���p�E�s�s�_�Ȃǂ̕]�_�����ɏ]���B
��Ȓ����Ɂw�A�[���E�k�[�{�[�̐��E�x�i�������_�Ёj�w���{�̃A�[���E�k�[���H�[�x�i�y�Ёj�w���I���̊X�p�x�i�����V���j�w���_���s�s�����x�i�������Ɂj�w1920�N�̉�Ƃ����x�i�V���Ёj�w���[���b�p�̗U�f�x�i�ۑP�j�w���_���E�f�U�C���O�j�x�i���p�o�ŎЁj�wLA�n�[�h�{�C���h�x�w�n���E�b�h���e�H��x�i�O���[���A���[�o�ŎЁj�w�A�d�̐��E�j�x�w�X�p�C�̐��E�j�x�w�Z���u�̌���j�x�i���Y�t�H�j�w���̓������i�x�i�E�����@�j�w�V�ҁ@�����̐����x�w�؏p�t�̓`���x�w�S�ݓX�̔����j�x�w�m�Ԃ̗��͂邩�Ɂx�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j���B�����W�Ɂw�c�������長�x�i�p�쏑�X�j�w�]�˂܂ڂ낵���q�x�w�]�˂̗[�f�x�i�͏o���[�V�Ёj�Ȃǂ�����B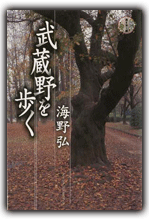
����������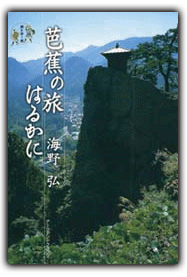
�m�Ԃ̗��͂邩��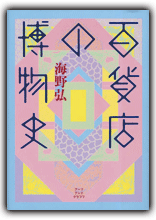
�S�ݓX�̔����j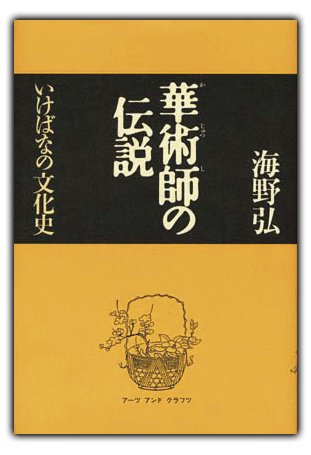
�؏p�t�̓`��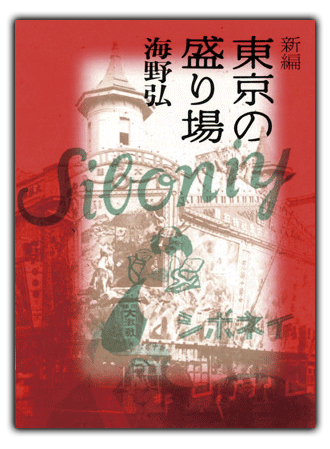
�V�ҁ@�����̐�����y�� �˕��i��������E���傤�ւ��j 1983�N�A�k�C�����܂�B�����w���|�w���y�����B���m�i���w�j�B���͖����w�B��Ȓ���Ɂw�̐l���q�̖����w�x�i�א��o�ŁA2017�N�j�A�w�����w�̎v�l�@�x�i���Ғ��A�c��`�m��w�o�ʼn�A2021�N�j�A�w�S��X�|�b�g�l�\����ɂ��������杂̎��ԁx�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2023�N�j�A�w�����Â炳�̖����w�\����̒��̍��ʁE�r���𑨂���x�i���Ғ��A���Ώ��X�A2023�N�j�A�_���Ɂu���ȁE�����E����\���݂��j�w���鎋�_�v�i�w����v�z�x5�����A2024�N�j�A�u�w�Q�x�Ƃ�����������̖����w�v�i�w���݊w�����x9�A2022�N�j�A�u�Q���Ɛ����ω��v�i�w�����w�������I�v�x45�A2021�N�j�ق������B 
����̉��ق��邢�͉��ق̌���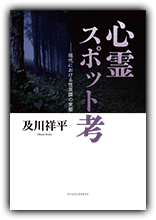
�S��X�|�b�g�l�哇 �A�u�i�������܁E�Ђ낵�j 1948�N�������܂�B���{�@��{�Ŗ쑺����̎w�����A�������|�w���w�сA�S���e�n�̘̐b���L�^����B�̘b�A�`���A���_�A�ߑ�ɂ�����O���̘b�̎�e�ƓW�J�A����`���̕��͓��ɂ��Ă̘_��������B�����w���b�\�`���̌����x�i�O��䏑�X�j�A�Ғ��Ɂw�쑺����@���ٓ`����ǂ݉����x�w���ٓ`��杁x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�ȂǁB���݁A�̘b����u�哇�m�v�A�u�l�G���̉�v��ɁBNPO�@�l�u���肽���̉�v�ANPO�@�l�u�S���{���l�b�g���[�N�v�����B 
�쑺����@���ٓ`���̐��E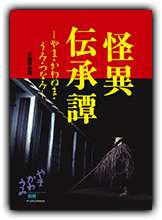
���ٓ`���
�\��܁E����ʂ܁E���݁E�Ȃ݁\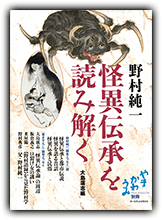
�쑺���� ���ٓ`����ǂ݉���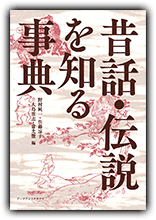
�̘b�E�`����m�鎖�T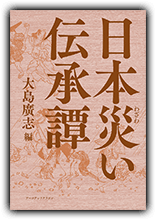
���{�Ђ��`������ �i�����ʂ��E������j �@�ʐ^�I�s��ƁB1933�N���܂�B�R�Ɵ�J�ЋΖ����o�āA�ʐ^�I�s��ƂƂ��Č��݂ɂ�����B
�@���{���Y�Ƌ������A���s�L�҃N���u����A���v���c�@�l ���{�Ԃ̉����B
�@��Ȓ����E�������Ɂw�S�� ���̖���100�I�x�i�Ƃ̌�����j�A�w���t �Ԃ̖��́x�i�����V���Ёj�A�w�ݗt�A�����T�x�i�N���I�j�A�w���t�̉Ԓ������x�i�W���Ёj�A�w�Ԙ@�i��}�Ӂx�i�������V���Ёj�A�w�Ԃ̖��t�W�x�i�O���t�B�b�N�Ёj�A�w�ޗǂ̉Ԃ���݁x�i���ƔV���{�Ёj�ȂǑ����B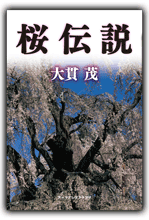
���`����� ���ǁi�����₵�E����傤�j �@1929�N�i���a4�j5��10��-2001�N�i����13�j4��12���A���N71�j�B
���{�̖����w�ҁA�_�b�w�ҁB�����s���܂�A���m���炿�B������w���_�����B������w�o�ϊw�����ƌ�A������w���m��������������A�����������ւāA1975�N����1990�N�܂œ������B���̌�1997�N�܂œ������q��w���㕶���w�������B���{�����w���A�k�C�����k�����������يْ������C�B�����Ȓ����Ɂw�_�b�w����x�w�הn�䍑�x�i�����V���j�A�w���̐_�b�x�i�O�����j�A�w�_�b�̘b�x�w�_�b�̌n���x�i�u�k�Њw�p���Ɂj�A�w�����̗������x�w��͂̓� ���̉˂����x�i���w�فj�������B���Ғ��Ɂw���{�̌Ñ�x�w���{����������n�x�i1996�N�x�����܁j�w�C�Ɨ����x���B
��ё��ǁ@�l�ގj�̍č\�����߂��������� �a�C�i������E���������j �����w�ҁE���|�]�_�ƁB1930�N���܂�B
���݁A������w���o�e�B�A�J�f�~�[�u�t�A���{���|�������A���{�y���N���u����B
��Ȓ����Ɂw���������̐��E�x�w�ɓ��×Y�x�i�u�k�Ёj�A�w�O�D�B�������x�i�����Ёj�ȂNjߑ�R��𒆐S�Ƃ����]����w�����w�x�i�V�����Ɂj�w���E�O�l�Y�̓����w�x�iNHK�o�Łj��w���̕��w�j�x�i���t���Ɂj�w���Ɠ��{�l�x�i�V���I���j�A�w���́E�^���́E�R�̂̎n���x�w���Ɠ��{�����x�w�ԂƂ��Ƃ̕������x�i�ȏ�A�A�[�c�A���h�N���t�c�j�ȂǑ����B 2014�N9��20�������B
�҈䋪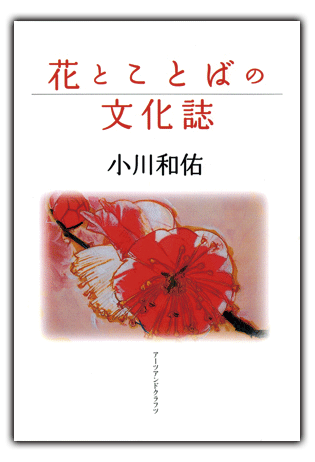
�ԂƂ��Ƃ̕�����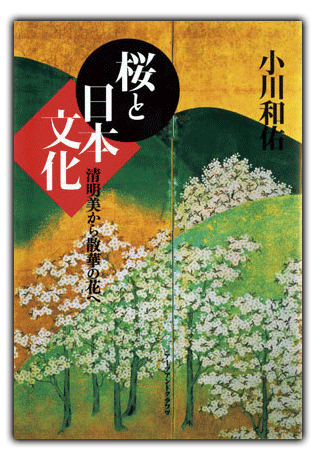
���Ɠ��{����![���́E�]���́E�R�̂̎n��](../../img/book/shadow/book_031.gif)
���́E�]���́E�R�̂̎n������ ���V�i������E�Ȃ��䂫�j �@���{�@��{���_�����E��w�@�q�������A���c���j�L�O�ɓߖ����w���������B���m�i�����w�j�B��Ȓ����E�w�n�斯���_�̓W�J�x�A�w�E�c���̖����w�I�����x�A�w���j�����_�m�[�g�x�i��c���@�j�A�w���{�̍Ύ��`���x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A�p��\�t�B�A���Ɂj�A�Ғ��E�w�܌��M�v�@���ƍĐ��A�����ď퐢�E���E�x�A�w�쑺����@�������|�̕����w�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w���{�̐H�����x1�E3���i�g��O���فj�A�w�u�����{�����w 1�@���@�Ɖۑ�x�A�w�u�����{�����w 5�@���Y�Ə���x�i���q���X�j�ȂǁB 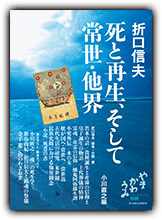
�܌��M�v�@���ƍĐ��A�����ď퐢�E���E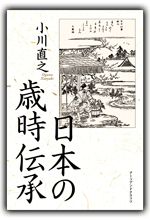
���{�̍Ύ��`��
�쑺����@�������|�̕����w
�����w����݂����
���s�F
-
�Љ� �`�j�i���������E�悵���j �@ 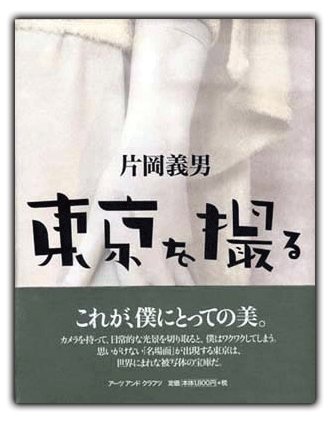
�������B�����q �m�i���˂��E�ЂƂ��j �@1958�N�A�Q�n���O���s���܂�B1984�N�A�w�Z�@�l����w���̎��c�t���ɏA�E�B�j�q���t�Ȃ�ł̖͂؍H�R�[�i�[��T�b�J�[�V�сA�T���V�т������Ɏ������B1995�N�A�w�Z�@�l����w���̎��c�t�������A�C�A�w�Z�@�l����w�������A�C�B2001�N�A�Вc�@�l�Q�n�������c�t��������A�C�B2013�N�A�Q�n�������\����܁B2023�N1���A�i���B 
���q�m���W���q �����i���˂��E�Ƃ����j �@1919�N�A��ʌ����܂�B�o�l�B�����o�d�I�ҁA����o�勦��_��B���{�|�p�@����B�������J�ҁB�����鍑��w�o�ϊw�����ƌ�A���{��s�ɓ��s�B1955�N�A��1��W�w���N�x�����s�A��5��o�勦���܁B1974�N�ɒ�N�ސE��A�o��ɐ�O�B2002�N�A��W�w�������x�Ŏ�┏�܁B2010�N�A��51���|�p�ܓ��ʏ܂Ƒ�58��e�r���܂���܁B���������B 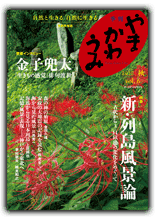
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6
���{�s�r �o�嗷���q �V�i���˂��E�䂤�j 1974�N�A��ʌ����܂�B�]�_�ƁA���������ҁB�w�f���̋���x�i�X�b�Ёj��2017�N�T���g���[�w�|�܁q�|�p�E���w����r��܁B�����Ɂw�Ӌ��̃t�H�[�N���A�x�i�͏o���[�V�Ёj�A�w�ً��̕��w�x�w�}�N���l�V�A�I�s�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�h�L�������^���[�f��p�x�w�x�y�̃N���e�B�V�Y���x�i�_�n�Ёj�A�w�����_�x�i�t�B�����A�[�g�Ёj�A�w���w�̃G�X�m�O���t�B�x�i�X�b�Ёj�A�w�C���f�B�W�i�X�x�i���}�Ёj�ȂǁB�Ғ��Ɂw�t�B�������[�J�[�Y�x�w�g�{�����_�W�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�����_�x�i�����Ёj�ق������B 
�Ӌ��A�W�A�̓��k���߂�����
�鋫�A�W�A�T�K�L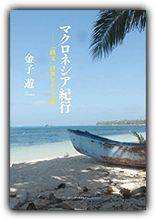
�}�N���l�V�A�I�s�u�ꕶ�v���E���߂��闷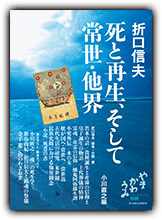
�܌��M�v�@���ƍĐ��A�����ď퐢�E���E
�ً��̕��w�@�����̕�������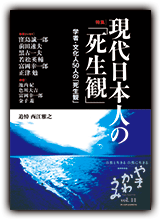
��� ���� ����
vol.11
�������� ���{�l�̋N����T�闷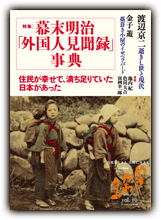
��� ���� ����
vol.10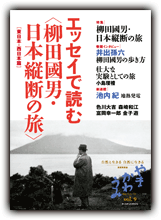
��� ���� ����
vol.9
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8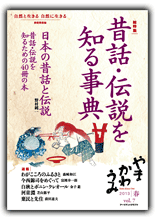
��� ���� ����
2013.�t�@vol.7
�g�{�����_�W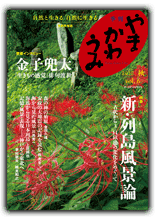
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6
�t�B�������[�J�[�Y��� �f���i���킮���E���Ȃ��j ���j�����Ɓi��U�͐퍑�E�]�ˎ���j�B���a36�N�A���R������B���R���ȑ�w���w�����w�ȁE�@����w���w���j�w�ȑ��B�@����w���_�������㒼���m�Ɏt���B����ɂ́A�w���얄�������؎��T�x�A�w���a�c�Ƃ̗��j�x�i�ȏ�A�V�l�������Ёj�A�w����œǂޑO�c���Ɓx�i�������o�Łj�A�w�{�{����101�̓�x�iPHP�������j�A���S���M�ɂ͑��㒼���ҁw�_�ސ쌧�����ƌn�厫�T�x�i�p�쏑�X�j�A���㒼�E�������j���ҁw���{�j�p��厖�T�x�i�V�l�������Ёj�Ȃǂ�����B 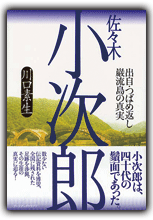
���X�؏����Y�쓇 �G��i���킵�܁E���イ�����j 1952�N���܂�B�{�錧�C����s�o�g�B�@����w�Љ�w�����ƁB���m�i���w�j�B���k��w�����}���فA�C����s�j�Ҏ[���A���A�X�E�A�[�N���p�فA�_�ސ��w���C�����A���k��w�ЊQ�Ȋw���ی��������������o�āA���������V�j�A�������B�����Ɂw�U�V�L�����V�̌�����Ƃ��x�i1999�j�A�w�ߗ�̖����x�i2003�j�A�w������閯���x�i2011�A�ȏ�O��䏑�X�j�A�w�����`���x�i2003�j�A�w�J�c�I���x�i2005�j�A�w�Ǎ����x�i2008�A�ȏ�@����w�o�ŋǁj�A�w�Ôg�̂܂��ɐ����āx�i2012�j�A�w������̃J�c�I���x�i2015�j�A�w�C�Ɛ������@�x�i2017�A�ȏ�y�R�[�C���^�[�i�V���i���j�ȂǁB 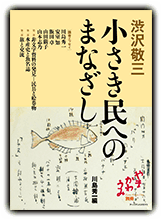
�a��h�O�@���������ւ̂܂Ȃ���
�{�c�o�@�����I���j�_��������c �����i���킽�E����ˁj 1940�N�A�����`�`�n���ɐ��܂��B59�N�A�_�ˍ����w�Z���ƁB62�N�A�����쉹�y��w���ށB69�N�A���W�w��̎��ԁx�����s�B�C�^���A�ɓn��B�t�B�����c�F�ɋ��Z���A�w�s�T�ʂ�x�w�O�t�x�Ȃǂ����s�B80�N�㔼�ɂ̓C���h�l�V�A�A����𗷂���B94�N�A���㎍���Ɂw��c�������W�x�B2000�N�O��ɂ͐��܂�̋��̒����ɗ�����B������E���Ɍ����K���B���̌�A�^�C�A���I�X�A���F�g�i��������B�܂��A���[�}�j�A�A�`�F�R�A�|�[�����h�Ȃǐ܂ɐG������B2015�N�A���W�w��̐��x�Ŕ����Y�܂���܁B���݂̓��F���[�i�ɋ��Z�B 
�h���D
�����̂Ƃ�̑��͏���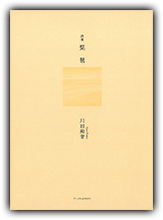
���W�@���i�_�c �p�h�i���E�Ђł̂�j 1978�N���܂�B�������H��w���{�l���t�B��ȖɁw���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n�ʁx�i����A�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�l���̋N�_�ƏI���w�x�i�A�����o�ŎЁj�A�w�u������o�v�Ɛ����Ȋw�Ɋւ����l�@�x�i�A�����o�ŎЁj�A�w�����W�̌��Ɖe�x�i����A���J�l���o�ŎЁj�A�w��Éq���T�[�r�X��p��Ζ�n���h�u�b�N�x�i����A����o�ŎЁj�ȂǁB 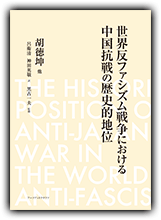
���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n��
�����@���w���W�j�k�c �K�b�i�������E�������j 1947�N�k�C�����܂�B1969�N�k�C�������w���ƁA1977�N�k�C����w��w�@���w�����Ȕ��m�ے��C���B1992�N�鐼���ۑ�w�������B2000�N�����B���݁A����w�q�������B�����Ɂw�����������@�]�˂��疾���̃��f�B�A�E���w�E�W�F���_�[��ǂށx�i�{�Y���сA2007�N�j�A���Ғ��Ɂw�R�W�����̕���@�������^�ƌ�蒼���x�i�{�Y���сA2002�N�j�B 
�t�F�~�j�Y���^�W�F���_�[��]�̌���
���㏗�����w��ǂ�
�R�W�����̌���C�J ���i�����ɁE�܂��Ɓj ���p�j�ƁBBIBLIOTHECA GRAPHICA��ɁB�ߋ���Ɏ�l�B�����Ɂw���i��̕a�Պw�@���������ƃp���̓��ʼn�x�i���}�Ёj�A�w�����Ƃ̃x���E�G�|�b�N�@�A�����E�x�����f�B�Ƃ��̎���x�i�}���o�ŎЁj�A�����Ɂw�ΊG�V�l�@�ЊQ�̃R�X�����W�[�x�i�}�g���сj�ȂǁB2008�N9��22���i���B 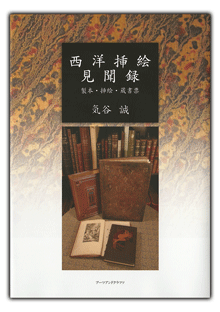
���m�}�G�����^�k�� �C��i�����́E�����j 1963�N�A���m�s���܂�B�����w�@��w���B1986�N�A������Ѓ��{����Z���^�[���ЁB�����W�c�E�����y�c�A�Y�p�����y�c���k�C���c��ɁB���݁A�J��匤����N�l�B�u���c����ǂށv���N�l�E�ψ��B���ꔭ�̋G�����w���x�ɘ_�l�\�Ȃǂ��Ă���B 
���v�z�̏C���w�@�J���Ə��c���𒆐S���ߑ㕶���j������i�����Ԃ����イ�����j 
�������50�l�̌��t�E�� ����Y�i���ڂ��܁E���������낤�j 1941�N�A�������܂�B����H�A����o�c�Ȃǂ��ւāA1979�N�A���쌧��c�s�ɚ�܉�Ƃ̑f�`��W������u�M�Z�f�b�T���فv��n�݁B1997�N�A�אڒn�ɐ�v��w���ԗ���p�فu�����فv���J�݁B2005�N�A�u�����فv�̊����ɂ���53��e�r����܁B2016�N�A���a�^���ւ̍v���ɗ^�������1�a(�Ƃ�)�t���[�`�����X�g��܁B�����Ȓ����Ɂw���ւ̎莆�x�i�}�����[�j�A�w�M�Z�f�b�T���ٓ��L�x�T�`�W�i���}�Ёj�A�w�����ق��̂�����x�i��46��Y�o�����o�ŕ�����܁E�u�k�Ёj�A�w�C�ƞő��x�i��14��n���o�ŕ������J��܁E�M�Z�����V���Ёj�A�w���@����ׁx�w��ӂ���x�w���؋L�x�i�����Ёj�A�w��܉�ƃm�I�g�x�w�N�W���y�x���W�w�����Â���x�w�E������Y�R���N�V�I���i�S5���j�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�ȂǑ����B 
�����Ƃ���������̂ց@�E������Y�u�⌾�v�Βk�W
�ǂނ��� �ς邱��
�����̈ꏑ�@��Ƃ������ǂl���Ō�̖{
�E������Y���W�@�̂����Ă䂭����
���p�����с@�E������Y�R���N�V�I���X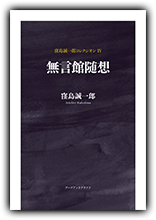
�����ِ��z�@�E������Y�R���N�V�I���W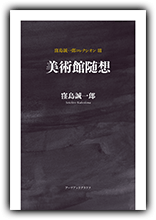
���p�ِ��z�@�E������Y�R���N�V�I���V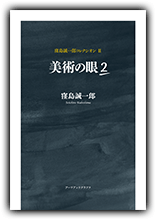
���p�̊� 2�@�E������Y�R���N�V�I���U
���p�̊�@�E������Y�R���N�V�I���T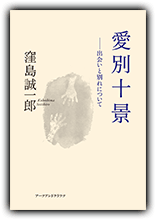
���ʏ\�i
�E������Y���W�@��������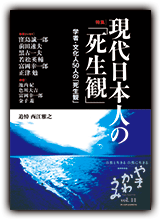
��� ���� ����
vol.11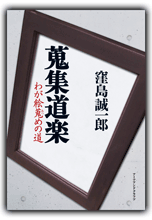
�N�W���y
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8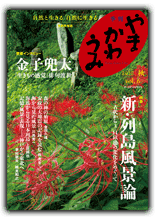
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6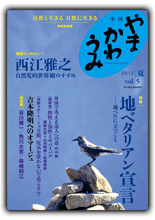
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5
��܉�ƃm�I�g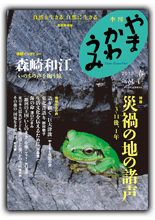
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4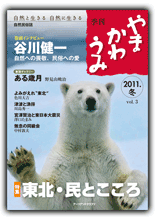
��� ���� ����
2011.�~�@vol.3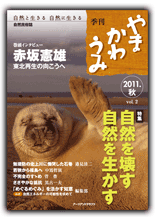
��� ���� ����
2011.�H�@vol.2
��� ���� ����
�n����2011.��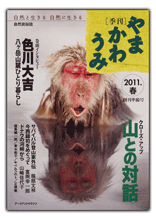
��� ���� ����
�n��������2011.�t�H �q�q�i���߁E�Ƃ����j �@ 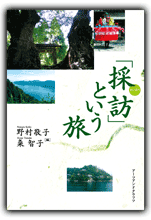
�u�̖K�v�Ƃ������v�� ��Y�i���߁E�܂����j 1948�N�A���Q�����܂�B�l�Êw�E���j�w�E��w�ƁB1970�N�����ّ�w���w���j�w�ȑ��ƌ�A���{����ψ�������ی�ې��E���i�l�Êw�E���p�H�|�j���o��2008�N�����|�p��w�q�������B2001�N�����ّ�w��蔎�m���k���w�l�A2010�N��4��Ï܁A2013�N��15�{�����������㎖�Ɠ��I�A2014�N���������Ж��_�Ј��A����B���������ِݗ���������ݓW�����ψ��A���݁A�����ː����E�J�y���p�ٕ]�c���A�����L���V�^���}�����s��ҏW�ψ��A������͕�����������ɁB�����Ɂu���{�Ñ���v�i�������j���������فj�A�w���{��͎j�̌����x�i�Y�R�t�j�A�u���{�����w�̘H�x�ƃy���V�A�����̔��Q�v�i�k��B�s�����{�����L�O�فj�A�w�͂x�i�@����w�o�ŋǁj�A�|��_���Ɂu���{�ޗǖ@�������B����\���l�v�u���{�N��l�v�i�����Ёj�Ȃǂ�����B 
���{�����q�`�ƌÑ�A�W�A�r�j�l���� ��v�i���낱�E�������j 1945�N12���A�Q�n���ɐ��܂��B�Q�n��w����w�����ƁB�@����w��w�@�ŁA���c�؏G�Y�Ɏt���B1979�N�A�C�m�_���������������w�k�����J�_�x�i�~���Ёj�����s�A��]�Ƃ̎d�����n�߂�B���|�]�_�ƁA�}�g��w���_�����B��Ȓ����Ɂw�����a���`���x�w��]���O�Y�`���x�i�͏o���[�V�Ёj�A�w�ы��q�_�x�i���{�}���Z���^�[�j�A�w����t���x�i�א��o�Łj�A�w���� �O�Y���q�_�x�i��䂎Ёj�A�w�w1Q84�x�ᔻ�ƌ����Ƙ_�x�w���̐���蒆����`���x�w����t���ᔻ�x�w�����a���̕��w�x�w�u�c��v�̕��w�x�w���È�v�@�ߌ����Ƙ_�W�x�S6���i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�҈䋪�_�x�i�_�n�Ёj�A�w�j�ՂƏC���\�S�������w�_�x�w��]���O�Y�_�x�w�������w�_�x�w���w�҂́u�j�E�t�N�V�}�_�v�x�w�䕚����Ɛ푈�x�i�ʗ��Ёj�A�w�������w�j�E�_�x�i�Љ�]�_�Ёj�A�w�H�B�{�����v�̋O�Ձx�i�o�ŎЁj�������B 
�ݓ����N�l���w�_
���}�g�������ꕶ�w�@��闧�T�@���g�h��@�ڎ�^�r
�u�ĐՐ���v�̕��w�@�����a���@���c���@�^�p�L�F�@�J����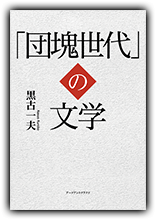
�u�c��v�̕��w
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��6��
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��5��
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��1��
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��4��
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��3��
���È�v �ߌ����Ƙ_�W�@��2��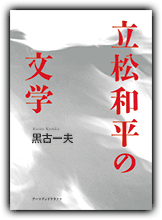
�����a���̕��w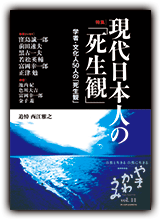
��� ���� ����
vol.11
����t���ᔻ
���̐���蒆����`��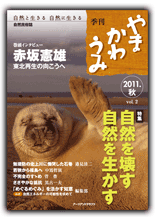
��� ���� ����
2011.�H�@vol.2
�w1Q84�x�ᔻ�ƌ����Ƙ_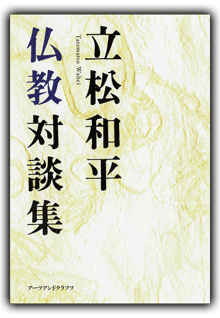
�����a�� �����Βk�W���� �㔪�Y�i�����炵�E���͂��낤�j 1944�N�A�H�c�����܂�B����c��w���B�w�S���̋����X�x�w���\�Y�x�w����z�̑I���x�u�����Ă�ł�v�����ꂼ�꒼�؏܌��ƂȂ�B1995�N�A�w�Y�������̂�����x�ŋg��p�����w�V�l��܁B2010�N�A�w�^�K������x���f�扻�B�w�I�N�ɂ͎��炸�@�V�������l��`�x�i�u�k�Е��Ɂj�A�w�ӂԂ��ǂ��x�i���w�فj�A�w���Ђ����x�S5���i�͏o���[�V�Ёj�A�̏W�w�����������x�i�Z�̌����Ёj�Ȃǒ��ґ����B�ߔN�́A�w�������x�w���A���ɏ}���x�w�����\�Ȃ��g�̈ł���āx�i�Ƃ��ɍu�k�Ёj�A�w�V�̂������ƂȂ��Ɍ��̂Ă�x�i�͏o���[�V�Ёj�A�w����A�Ⴋ�܉E�q��x�i�u�k�Ёj�Ȃǂ̗��j�����A�܂��̌��I�V���������w�ޕ��ւ̖Y����́x�w����͒N���ĂԐ��x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�����s�B 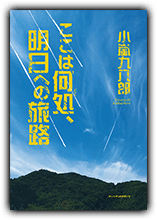
�����͉����A�����ւ̗��H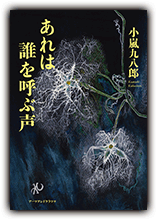
����͒N���ĂԐ�
�ޕ��ւ̖Y������� �b���i���E�������傤�A�E�[�E�t�F�C�E�V�@���AWu Huisheng�j 1989�N�A�����E�R���Ȑ��܂�B2016�N�A����O���l���w���Ƃ��ė����A������w��w�@���w�����ȓ��{���w��U�ɓ��w���A�w�������{�z�����̂��ƂŁA2019�N3�����m����ے��C���B���m�i���w�j�B���݁A�������ȏ���B���{�ߑ㕶�w�E�푈���w��U�B��v�_���ɁA�u�ΐ�B�O�u�����Ă�镺���v�ĕ]���\�����̕]���j���r���Ȃ���\�v�i�u�Љ�w�v��46���A2017�N7���j�A�u�펞���ɂ�����ΐ�B�O�́u�푈���́v�\���{���w��𒆐S�Ƃ����u���|�e��^���v�Ƃ̊ւ������Ɂ\�v�i�u���w�����_�W�v��48���A2018�N2���j�A�u��́u���v�\�펞���ɂ�����ΐ�B�O�́u�푈���́v�A�u���p�v����s��܂Ł\�v�i�u���w�����_�W�v��49���A2018�N9���j�Ȃǂ�����B 
�ΐ�B�O�̕��w
��O������ցA�u�Љ�h��Ɓv�̋O������ ���X�i�����܁E�悵�䂫�j 1935�N���܂�A�_�ސ쌧�o�g�B���c���j�E�܌��M�v�̊w��ɂ�������A���{�@��{���w���i�w�A�������O�Ɏt���A�����w�I�ȓ��{�ÓT���w���U�A��w�@���m�ے��C���B������w����w���E��w�@�ŁA���{�ÓT���w�E�����w��S���A���݁A���_�����B�����w���|�w�����u�t�A�������w�������q��������C�B�i�����j�������ꂨ���Ȃ�^�c���c�@�]�c���B ��Ȓ����E�Ғ��ɁA�w�ĎR�q�n�}�x�w�_�ސ쌧��蕨�����x�w�����̘b�W�x�w�Z�����y�L�x�w�����w�̎��p�x�w���{�̐_�b�x�w�����������w�̌����x�w���{��ًL�x�w�ւ̉F�����x�w�l�E���E�E�n�x�w���z�ƈ�̐_�a�x�w�L�̉��x�w�̎O�������x�ق��B 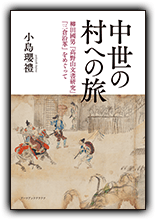
�����̑��ւ̗��\���c���j�w����R���������x�w�O�q���v�x���߂������㓡 ���i���Ƃ��E������j 1954�N�A�{�錧���s���܂�B������w�ōl�Êw���U�����w�C�m�B�n���C��w�Ől�ފw���w��Ph. D.�i�l�ފw�j�B�{��w�@���q��w�A���u�Џ��q��w���o�āA��R��w�l���w�������B����Ɂw�C�̕����j�x�i1996�A���ҎЁj�A�w�n���C�E�쑾���m�̐_�b�x�i1997�j�A�w�쓇�̐_�b�x�i2002�A�ȏ㒆�����_�Ёj�A�w�u�������v�������x�i1999�A���w�فj�A�w�����l�Êw�x�i2001�j�A�w�J���n���n�剤�x�i2008�A�ȏ�א��o�Łj�A�w�C��n���������S���C�h�x�i2003�j�A�w�C���猩�����{�l�x�i2010�j�A�w���E�_�b�w����x�i2017�A�ȏ�u�k�Ёj�A�w�V���̍l�Êw�x�i2017�A�����Ёj�ACultural Astronomy of the Japanese Archipelago : Exploring Japanese Skyscape�i2021, Routledge�j�ȂǁB 
��ё��ǁ@�l�ގj�̍č\�����߂������� �����i���E�Ƃ�����j 1946�N3���A�Ζk�Ȑ��B�s���܂�B69�N������w���j�w�����ƁB88�N������w���j�w�������A�C�B������w���w�������o�āA���݁A������w�����Ӌ��E�C�m�����@�@���B���s��w�K��w�ҁA�n����w�K��w�ғ����C�B ���N�A����E���j�A�����푈�j�A�卑�C�m�j�A�����C�d�j�̌����ɏ]���B��Ȓ����Ɂw����E���j�ԁx�A�w�����푈�j�i1931-1945�j�x�A�w���t�@�V�Y���푈���ɂ����钆���Ɛ��E�Ɋւ��錤���x�i�S9���A�ҏW���j�A�w���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n�ʁx�ȂǑ����B 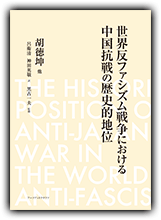
���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n������ �x�v�q�i���₵�E�ӂ����j 1943�N���{���܂�B1967�N�m�[�X�J�����C�i��w�p���w�ȑ��ƁA1968�N���O�����w�p��ȑ��ƁB1972�N�ɑ���c��w���w�����Ȕ��m�ے������ފw�B�n�[�o�[�h��w�A�J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�Z�q���������B1981�N��葁��c��w�����B���ݑ���c��w���_�����A�鐼���ۑ�w�q�������B�����Ɂw�~�n���q�@�W�F���_�[�œǂލ�Ƃ̐��ƍ�i�x�i�V�T�ЁA2005�N�j�ȂǁA�Ɂw�����̂Ȃ��̉������ց@�ڏZ�E��E���E�I�o�����x�i�g�����ET�E�~���n�A���}�ЁA2014�N�j�ȂǁB 
�t�F�~�j�Y���^�W�F���_�[��]�̌���
���㏗�����w��ǂ�
�R�W�����̌��
���s�F
-
�� ���j�i�������E�������j �@1949�N�A�{�錧�Ί��s���܂�B���k��w��w����� ���s���a�@�Ζ��A���k��w��w�������ȍu�t�A���k��w�t���a�@���Y��q�Z���^�[�������A�{�錧�����ǂ��a�@���@�������o�āA2008�N9���u�������������E�Ԃ���ǂ��N���j�b�N�v���J�ƁB���͐V�����w�A�ċz�����w�A��ʏ����ȁA�������B�w�B�uNPO��a�̂��ǂ��x���S���l�b�g���[�N�v�^�c�ψ��A�Вc�@�l���{����̉���A�{�錧�����Ȉ�����B
�@�����Ɂw�����H�x�w���S�̕���玙�x�i�ȏ���{����̉�j�A�w���������܂ꂽ�Ԃ����̈��S�玙�x�i�x�l�b�Z�Ёj�A�w�C���X�g�Ŋw�ԐV�����̑�\�I�����Ɛ����x�A�w�V������å�Ō�̗Տ���Z70�x�i�ȏチ�f�B�J�o�Łj�Ȃǂ�����
�@�z�[���y�[�W�@http://www.stbcc.jp/index.html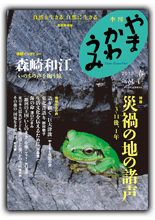
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4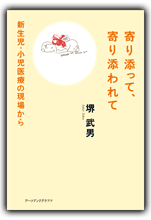
���Y���āA���Y�������䒉�N�i�������E�����₷�j 1941�N�A�k�C���]�s�ɐ��܂��B64�N�A�c��`�m��w���w�����ƌ�A�_�ސ쌧���ߑ���p�قɋΖ��B92�N�A���يْ��B2004�N����2024�N�܂ŁA���c�J���p�يْ��߂�B��Ȓ����Ɂw�C�̍��x�i���X�j�A�w�J�Ԃ̕����G�t ���e�x�i���肩���[�A��1��T���g���[�w�|��܁j�A�w�����Ƃւ̎莆�x�w����Ƃ��������w ���V�r�b�L�x�i���m�J�j�A�w��ѕ� ���ɂȂ��������Ɓx�w�|�p�̕⏕���x�i�݂������[�j�A�w�����̓V�ˉ�� ���{�ߑ�m��̏\��l�x�i�����V���j�w�o�� �����E�����̔��p�x�i��g���㕶�Ɂj�A�w���p�̐X�̔Ԑl�����x�i�������j�A�w�]���ƏƉ� ���Z���m�[�g�x�i���}�Ёj�ȂǑ����B 
�����̃X�P�b�`�u�b�N���� ���i�i���Ƃ��E�����j �@ 
�����B�����s���� ����i���Ƃ��E���������j 1954�N�H�c�����B1977�N����c��w����w�����ꍑ���w�ȑ��ƁB1982�N�k�C����w��w�@���w�����ȏC�m�ے��C���B1995�N�H�c��w����w�����u�t�B���ݕ��|��]�ƁB ��Ȓ����A�w�u�����a���w�j ��2���x�i�L�����A1988�N�A���S���M�j�A�w���_�j�X�g�ɓ����x�i�L�����A1992�N�j�A�w����ʓ��{���w�j���T����сx�i�������A1999�N�A���S���M�j�A�w���яG�Y�̃��A���@�n����]�́s��ٍ��m�t�x�i�ʗ��ЁA2016�N�j�A�w���яG�Y�̒��푈�\�S�߁w����Ƃ������x���y���ށx�i�Ŋ`���A2017�N�j�A�w���яG�Y�̔閧�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2019�N�j�ȂǑ����B 
�������̃I�[��
�S�b�z���l����q���g
���яG�Y�̔閧![���яG�Y�̔�]�|�p](../../img/book/shadow/book_092.gif)
���яG�Y�̔�]�|�p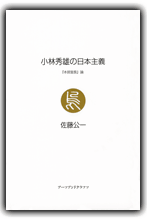
���яG�Y�̓��{��`
���яG�Y�̒�=�ߑ�
���яG�Y�̃R�A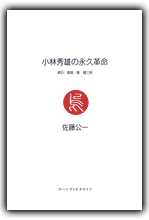
���яG�Y�̉i�v�v���Ɍ� ���i�����͂�E�Ђ낵�j ��t��w�Z����w�����_�����A���m��w�������y�������������B���a22�N�i1947�j���m���L���s��Β��ɐ����B���m�i���w�j���{�@��{�B���{�@��{��w�@���m�ے������ފw�B�����w�A��r�����w�A���y�j�w��U�B �����Ɂw�R�����Ɓw�юR��^�x�x2001�A�i�َЁB�w�������b�̔�r�����x2004�A���Ï��@�B�w�������b�̗��x�i�����j2011�A�O��䏑�X�B�w�R�����\�����Ƃ��̐��U�\�x2012�A�É��V���ЁB�w�V�Ł@�R�����Ɓw�юR��^�x�x2013�A��������o�ŕ��B�w�����w�_�x2014�A���Ï��@�B 
�|�����v�̔蕶�Ƙa������ �ׁi���傤�ÁE�ׂ�j 1945�N�A���䌧���܂�B���u�Б�w���w�����ƁB���l�E���M�ƁB�����Ȓ����Ɏ��W�w�S���x�i�����Ёj�A�w���Õ��W�x�i�v���Ёj�A�w���z���b�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�B�����w�����킹�݁x�w�͓���K�x�i�͏o���[�V�Ёj�B�]�`�w�R�����G�q�@�O�c�����x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�Y���ꂽ�o�l�@�͓��Ɍ�ˁx�i���}�АV���j�A�w��H�H�ʁx�w���`�t�x�w�����{�I�x�i��i�Ёj�ȂǑ����B 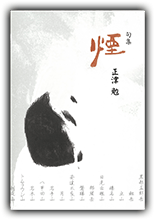
��W�@��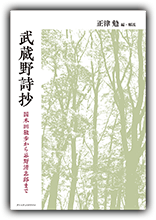
�����쎍��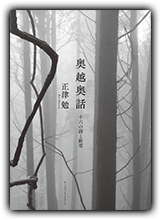
���z���b�\�\�\�Z�̎��ƒf��
���s���l�B�\�\���Z�Z�N�㎍�Y���L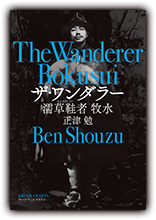
�U�E�����_���[�\�\�G���� �q��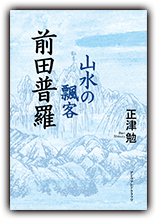
�R�����G�q�@�O�c����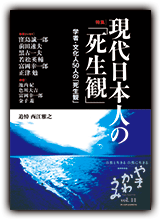
��� ���� ����
vol.11
�q���̗̕��b�V�R��
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8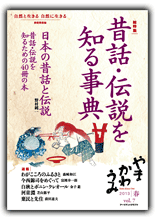
��� ���� ����
2013.�t�@vol.7
����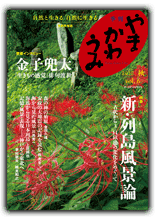
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6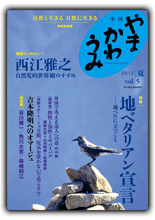
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5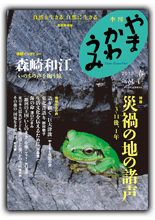
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4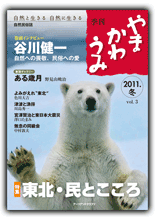
��� ���� ����
2011.�~�@vol.3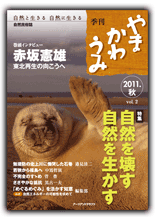
��� ���� ����
2011.�H�@vol.2
��� ���� ����
�n����2011.��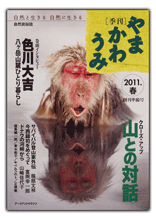
��� ���� ����
�n��������2011.�t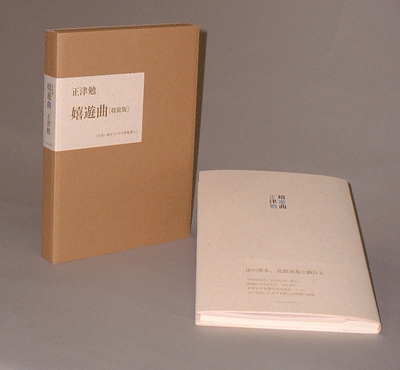
��V�ȁi�����Łj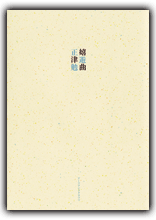
��V�ȁi���y�Łj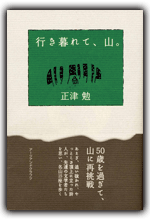
�s�����āA�R�B
�l�͂Ȃ��R���r���̂����� �u�[�i�����͂�E�䂫�Ђ�j 1951�N�R�`�����܂�B�w�K�@��w��w�@�����w�����Ȕ��m�ے��I���B���y�]�_�ƁB���݊w�K�@���q��w�u�t�i���{�����v�z�j��U�j�B���k���v������w�A�t�F���X���w�@��w�ő�O���y���e�[�}�Ƃ����r�v�z�u���S���B���y���Ƃ��ẮA�w���y�K���_�x�i�w�K�����Ёj�A�w���K�q�b�c�I�x�i�܂ǂ��o�Łj�A�w���b�N�����[���E�N���V�b�N�X�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�B�����Ɂw200�b�c�j���[�E�X�^���_�[�h�x�i�w�K�����Ёj�A�w�S�Ăs�n�o�q�b�c�M���{�x�i�w�z���[�j�A�Ƀ|�[���E�l�E�T�����ҁw�G�����B�X�Ƃ͒N���x�i���y�V�F�Ёj�ȂǑ����B 
���y�̋L��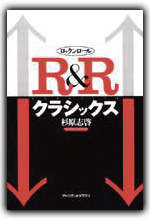
R��R�N���V�b�N�X��� �ӂ��q�i�������E�ӂ����j �������܂�B���|�]�_�ƁB�R�w�@��w���w���p�ĕ��w�ȑ��ƁB�t�F���X���w�@��w��w�@�l���Ȋw�����ȉp���w��U���m����ے��C���B2003�N�Ɂu�I�X�J�[�E���C���h�̞B�����\���̍�i�Ɍ�����L���X�g���I�v�f�ƃf�J�_���X�\�v�Ŕ��m���i���w�j�擾�B��w�̍u�t�߂Ȃ���A2008�N���u���̒Nj��ҁv��搂�ꂽ�W���j�[�E�E�B�A�[�𒆐S�Ƀt�B�M���A�X�P�[�g��厏�Ŏ�ށB���݁A���{��w�A�R�w�@��w�A���{�@��{�ʼnp��E�p���w�E��r���w���u����B�����Ɂw�I�X�J�[�E���C���h�̞B�����\�\�f�J�_���X�ƃL���X�g���I�v�f�x�i�J���ЁA2005�N�j�A�w�O���R�I�v�@���̉ցx�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2015�N�A���ە����\���w���܁j�A�����Ɂw��r���w�̐��E�x�i��_���A2005�N�j�A�w�������^�[��ǂށ\�\���̗̕��x�i��C�ُ��X�A2008�N�j���B 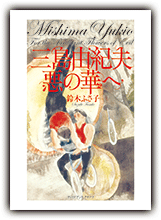
�O���R�I�v�@���̉�
�X��̃h���A���E�O���C�@�������j�q�t�B�M���A�X�P�[�^�[������ �a�F�i�����E�����Ђ��j 1946�N�A�����s���܂�B����c��w���w�����ƁB����w�@���w�����ȓ��{�j�w��U�C�m�ے��C���B95�N�w���{�Ñ�Љ���j�̌����x�Ś��{�@��{���m�i���j�w�j�B�������q��w�Z�E�����w�Z�Z���A���{�@��{���C�u�t�A�������Ñ㕶���Z���^�[�q���������A�����q�s�s�j�҂���ψ����C�B
���݁A���{�n�������������E���s���`�|�p��w�q�������E���������l�\��Y����Ĕ���������������E�_��s�������ی�R�c���B
��Ȓ����ɁA�w�הn�䍑�_�x�i�Z�q���[�j�A�w���y�L�ƌÑ�Љ�x�i�����[�j�A�w�ږ�āx�i�O�ȓ��j�A�w�Ñ�_���E�H��K�˂āx�w�Ñ�o�_�ւ̗��x�i�����V���j�A�w�Ñ�o�_���E�̎v�z�Ǝ����x�i��Е������ƒc�j�A�w�V�E�Ñ�o�_�j�x�i�������X�j�A�w�o�_�����y�L���_�x�i���Ώ��X�j�A�w�Ñ�ɍs�����j���肯��x�i����o�ŁE��P��Ñ���j�������܂ˏ�܁j�A�w�Ñ�Ό��̗U�����x�i����o�Łj�A�w�Ñ�o�_�̐[�w�Ǝ���x�i�����Ёj�B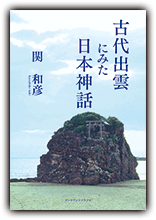
�Ñ�o�_�ɂ݂����{�_�b���ˌ� ��i�i���Ƃ����E�̂Ԃ��j �@1945�N����B���{�@��{���w�����ƁB���W�Ɂw�Y��̈��́x�i�~���Ёj�A�w�V���K�[���̊�x�i���O�i�[�o�Łj�A�w�����Ă��ܗ��̏I��Ɂx�i�n�юЁj�A�w���ɐ������x�w�Ό��x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�N�����m���Ă���c�c�x�i���s�Ɂj�ȂǁB�]�_�W�Ɂw�\���҂̉��L�\�����c�e�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�u���v�Ƃ����ꏊ�\�����E�������E��C�M���E���R�ő��x�i���s�Ɂj������B���{���Y�Ƌ���E���{���㎍�l��A���{���l�N���u����B�����������C�����B�����u����v���l�B 
���l�̍��@�v�ۓc�����Y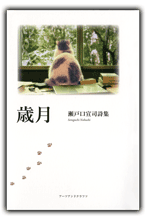
�Ό��@���ˌ���i���W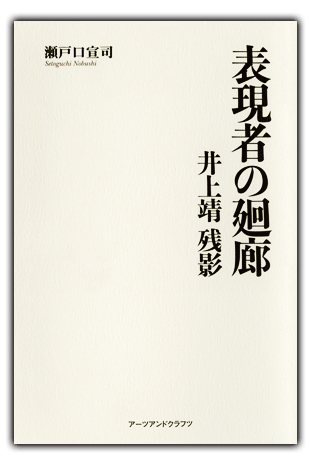
�\���҂̉��L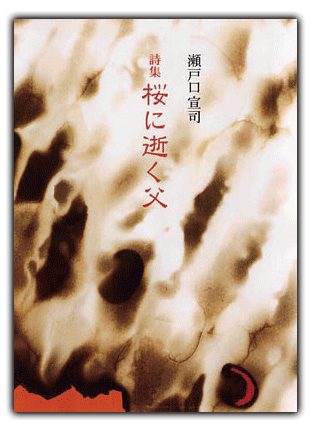
���W ���ɐ��������؎Ɂi������������j ���{��⊿����ɂ��āA���܂��܂Ȋp�x���猤�����Ă���W�c�B���݁A���{��̂Ȃ��ł̊����̎g��ꂩ���ׂĂ���B 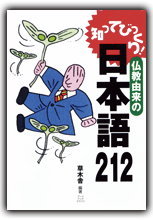
�m���Ăт�����I�����R���̓��{��212�h�ݖ��i���E�����߂��j 1987�N�A�����E�����s���܂�B2019�N9������w���Ƃ��ė����A������w���w�����Ȃɓ��w���A2025�N3�����m����ے��C���B���m�i���w�j�B���݁A�͖k�k���w�@�i�����E�͖k�ȁj���{��Ȑ�C���t�B���{�ߌ��㕶�w��U�B��������F���{�A���n���w�A���g�����w�A�������w�B 
�u���B�v�A���n���w�̌����h�q�ǁi���E����傤�j 1956�N�A��C���܂�B��C�t�͑�w���j�w�����B1991�N�`93�N�A������w�O���l�������B��C���{�w���A���ؓ��{�w��햱�����A�����u�Ԉ��w�v��茤���Z���^�[��C�A�����u�Ԉ��w�v���j�����ْ��B�����ɂ�������{�R�̏]�R�Ԉ��w����30�N�Ԍ������A�咘�Ɂw���R�u�Ԉ��w�v�����x�i�c���o�ŎЁA2015�N�j�A�w�싞���R�Ԉ������^�x�i�싞�o�ŎЁA2017�N�j�A�w�؋��F��C172�Ԉ����f��x�i��C��ʑ�w�o�ŎЁA2018�N�j�A�wChinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan�fs Sexual Slaves�x�i�����AUBS�F�J�i�_�A2013�N�G�I�b�N�X�t�H�[�h��w�o�ŎЁA2014�N�G���`��w�o�ŎЁA2014�N�j�Ȃǂ�����B 
���{�R�u�Ԉ��w�v���̌���
���s�F
-
���� �����i�����́E�͂��j 1948�N �É������܂�
1968�N �����H�ƍ������w�Z�@�B�H�w�ȑ���
�@�@�@�@���d�@��Ђɓ���
1977�N �����ȓ��n�������w���Ƃ��ă��L�V�R�ɗ��w
1995�N �u���W���E�T���p�E���s�ŁA���n�@�l�̌o�c�Ɍg���i�`2002�N�j
2002�N �����J���`���[�Z���^�[�̒ʐM�u���ŃG�b�Z�C�������n�߂�
2008�N ��N�ސE���A�N�������ɓ���
�@�@�@�@�ȁA����C�Ɖ��l�s�����ɕ�炷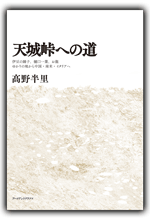
�V�铻�ւ̓����� �a���i���Ă܂E��ւ��j 1947�N�Ȗ،����܂�B����c��w���o�w�����ƁB�݊w�����A���|���ɏ����\�B70�N�A��1��c���w�V�l�܁i�u���]�ԁv�j�A80�N�A��2���ԕ��|�V�l�܁i�u�����v�j�A93�N�A��8��ؓc�������w�܁i�u���v�j�A97�N�A��51���o�ŕ����܁i�u�Ł\����E�c�������v�j�A02�N�A��31���J�|���Y�܁i�̕���u�����̌��v�̑�{�j�A07�N�A��35��ԕ��w�܁i�u�����T�t�v�j�A08�N�A��5��e�a�܁i�u�����T�t�v�j�����ꂼ���܁B
�w��l���͐l���݂������x�i2001�A�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�~���\�������q����`�x�i2006�A��@�֊t�j�A�w�ӔN�x�i2007�A�l�����@�j�A�w�����T�t�x�i�㉺�A2007�A�������Ё^�㒆���A2010�A�V�����Ɂj�A�w�l��������Ƃ���Ƀu�b�_����\�ڂ��̕�������\�x�i2008�A�S�}�u�b�N�X�j�A�w�e�a�Ɠ����x�i2010�A�˓`�Ёj�ȂǁB
2010�N2��8�������i���N62�j�B�u��@�ցv�A�ڒ��ł������w�NJ��x�ƁA�������낵�̏����w������ �����E�c�������x�������̐�M�ƂȂ�B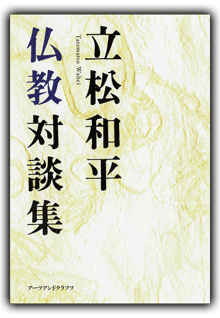
�����a�� �����Βk�W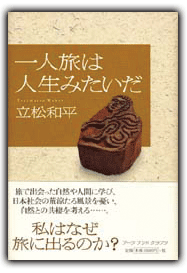
��l���͐l���݂������c�� �a���i���Ȃ��E�������j 1974�N�A�x�R���܂�B���|�]�_�ƁA�@����w�����B�c��`�m��w�o�ϊw���A���w�������ȑ��ƁB2000�N�A�]�_�u��������\�]���~�_�v�ő�7��O�c���w�V�l�܂���܁B�����Ɂw�]���~�x�i�c��`�m��w�o�ʼn�j�A�w���̐����z���ā\���{���㕶�w�_�x�w�V�Ɏ��x�i�u�k�Ёj�A�w�g�{�����x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�k�Ќ�̓��{�Ő푈������������x�i���㏑�فj�A�����Ɂw�g�{�����_�W�\�����E�����E�����_���āx�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j������B 
�g�{����
�g�{�����_�W![�Ȃ����|���]�͏I���̂�](../../img/book/shadow/book_194.gif)
�Ȃ����|���]�͏I���̂��J�� ��i���ɂ���E����j 1923�i�吳12�j�N�A�F�{���������ɐ��܂��B�{���A�ށi���킨�j�B�����F�{���w�Z�A��܍����w�Z���o�ē����鍑��w���w���Љ�w�ȑ��B1945�i���a20�j�N�`47�N�A�����{�V���ЂɋΖ��B47�N�A�ێR�L�A�����ς�̎����u�ꉹ�v�ɎQ���B50�N�A���j�ŋA���A�×{�����𑗂�B58�N�A���������Ԏs�ŏ��p�M�E�X��a�]��Ɓu�T�[�N�����v��n���B60�N�A���Ԏs�̑吳�z�ƘJ���҂����������吳�s�����A����ёސE�ғ������x���A�w������B65�N�A�㋞���ăe�b�N�i�̂����{����Z���^�[�j�ɓ��ЁA�q�ǂ������̊O����K���ɔ����\�������Ɍg���B81�N�A�\��̉�A82�N�A���̂����蕶���̉��n���A�{���̓��b��f�ނɎq�ǂ��Ƒ�l���Ƃ��ɎQ������\��������W�J����B1995�i����7�j�N2���A�����A���N71�B 
�s�m�ΊC�ւ̎莆�J�� ����i���ɂ���E�����j �@1921�N�A�F�{�������s���܂�B������w���w�����ƌ�A���}�Ђɓ��ЁA�u���z�v����ҏW���߂�B�����w�ҁA�̐l�A���{�n���������A�ߋE��w�����w�������̏��㏊���B�������J�ҁB2013�N8��24���A�����B�w�쓇���w�����_�x�Ō|�p�I��������b�܁A��2�����F��܁B�w���{�������������W���x�w���{����������n�x�Ŗ����o�ŕ����܁B�w�J�쌒��S�W�x�S24���ȂǁB 
�J�쌒��
���̊҂鏈�m����V�Łn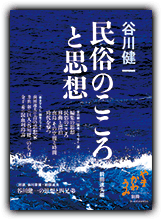
�J�쌒��
�����̂�����Ǝv�z
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8
���̊҂鏈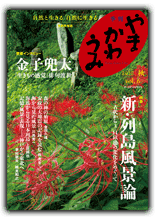
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6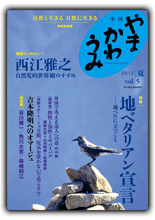
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5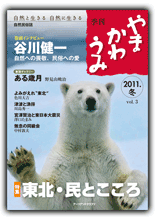
��� ���� ����
2011.�~�@vol.3�J�� �r���Y�i���ɂ���E����낤�j 1931�N�A�����������܂�B���N����莍����͂��߂�B���āA��ԎR�k�[�̖k�y���ɑ؍݁B���n�ɂ����ď����ꂽ��i��52�N�A��ꎍ�W�w��\�����N�̌ǓƁx�A53�N�w62�̃\�l�b�g�x�A93�N�w���Ԓm���Y�x�ȂǂɏW�^�B�Ȍ���܂ɂ��A���̒n�ɑz���������s���W�ɔ��\���Ă���B�܂��w�i���Z���X�E�J�^���O�x�ق��ɏ��i�����ځB 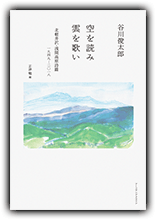
���ǂ݁@�_���̂�
�k�y���E��ԍ������ш��l��\��Z�ꔪ�c�R �È�i����܁E������j �@1931�N�A���l�ɐ��܂��B48�N�A�_�ސ쌧�����{�ꒆ�w�Z���ƁB52�N�A��ꐅ�Y�u�K���i���E�����C�m��w�j�����Ȃ𑲋ƁB���N�A�O�Y�s�O�苛�s����̐_�ސ쌧�������Ƌ����g���ɓ��Ђ��A22�N�Ԃɂ킽��C�O��n���ƁA�������Ƃɏ]������B75�N�A�����n��Ƃɓ��Ђ��A�}�O���̕ۊǁE���H�E�̔������ɏ]������B87�N�A���ۋ��ƊJ�������C�����ɏA�C�B���m�C�J���Ƃ̉^�c�Ɍg���A90�N�Ɏ��C�B
�@�����Ɂw�T�V�~�܂���x�i���{�Z���t�T�[�r�X����A79�N�j�A�w�}�O���̘b�x�i�����o�ŁA81�N�j�A�w���}�O���̘b�x�i�����o�ŁA82�N�j�A�w�����x�i��w�̗F�ЁA87�N�j�A�w���l�̓����x�i�A�h���u�A92�N�j�A�w�O��}�O�����y�L�x�i99�N�j�A�w���������x�i2005�N�j�A�w�Ό��̍ʂ�x�i2010�N�j�A�w�Ȃ�ӂˁx�i2012�N�j�i�ȏ�A�[�c�A���h�N���t�c�j������B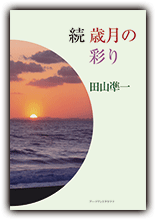
�� �Ό��̍ʂ�
�Ȃ�ӂ�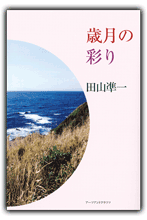
�Ό��̍ʂ�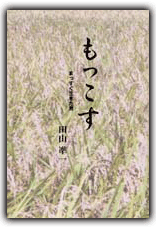
��������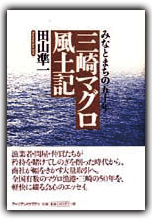
�O��}�O�����y�L�� �m���i����E�������AChen Zhiqing�j 1988�N�A�����E��z�s���܂�B2018�N10���A����w���Ƃ��ė����A2019�N4���A�����w�|��w��w�@�A���w�Z����w�����Ȃɓ��w���A�w���������c�`�������̂��ƂŁA2022�N3�����m����ے��C���B���m�i�w�p�j�B���݁A�Ζk������w�i�����E�Ζk�ȁj���{��Ȑ�C���t�B���{�ߑ㕶�w��U�B 
���蓡���\�u�v�Ɓu�Љ�v�̑���������� ���i�Ƃ���E�������j 1956�N�A�������܂�B��w���ƌ�A�����Z�@�ւɓ���A���ە��储��у��e�[������ɏ]�����ސE�B���w�Z�̍����N���V�b�N���y�ɐe���݁A���t��ɒʂ��ƂƂ���LP��CD�̎��W�ɗ�B�܂��A�t�����X���w��C�O�Ζ��i�V�J�S�Ȃǁj�̐܂́A�N���V�b�N���y�̉��t��ɐ������e���B�ꎞ�������c�ɓ����ď@���Ȃ��̂�����A�v���̐搶�ɂ��ă��R�[�_�[���K�����肵�����Ƃ�����B���L����CD�ELP��3,000���ȏ�ɂ̂ڂ�i�������A���m�ɐ������킯�ł͂Ȃ��A���Ԃ͂悭������Ȃ��j�B�����Ɂw�N���V�b�N���y�̊��������߂ā\�܂ݐH���I�ӏܖ@�̂����߁x�i2023�N�A�A�[�c�A���h�N���t�c�j������B2024�N6��10���A�i���B 
�N���V�b�N���y�̊��������߂�
���N���V�b�N���y�̊��������߂��x�� �K��Y�i�Ƃ݂����E���������낤�j 1957�N�������܂�B���|�]�_�ƁB�֓��w�@��w���ە����w����r�����w�ȋ����A���q���w�يْ��B������w���w�������ȑ��ƁB��22��Q���V�l���w�ܕ]�_����D�G���܁B����簂̌l���w�����ҁx�i1994�`2005�j�A��p���w�\���ҁx�i2005�`2018�j�ɎQ���A�w�\���ҁx�ł͕ҏW���߂�B
�����w��㕶�w�̃A���P�I���W�[�x�i�������X�A1986�N�j�A�w�����ӎO �̑�Ȃ�ߐl�̐��U�x�i�V���[�Y���ԓ��{�w��15�F���u���|�[�g�A1988�N�^�������ɁA2014�N�j�A�w��]�̌��݁x�i�\�z�ЁA1991�N�j�A�w���ʂ̐_�w�\�O���R�I�v�_�x�i�\�z�ЁA1995�N�j�A�w�g�k�I�l�ԁ\�J�[���E�o���g�x�i�u�k�ЁA1999�N�^�u�k�Е��|���ɁA2012�N�j�A�w�ł��̂߂����悤�Ȃ����������x�i�V�ЁA2003�N�j�A�w���_�x�iNTT�o�ŁA2004�N�j�A�w���|�]�_�W�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2005�N�j�A�w�X�s���`���A���̖`���x�i�u�k�Ќ���V���A2007�N�j�A�w��N�c����{��ցx�iNTT�o�ŁA2012�N�j�A�w�Ō�̎v�z�@�O���R�I�v�Ƌg�{�����x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2012�N�j�A�w�k�̎v�z�@��_���Ɠ��{�l�x�i���ЍH�[���R�A2014�N�j�A�w��[�N���@���E�̕��w�x�i��g���X�q��g����S���r�A2014�N�j�A�w���ς́u���v�x�i�_�n�ЁA2017�N�j�A�w�����ƒ��ρ\��݂����鍡���юi�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�A2019�N�j�A�w�V�c�_�@�]���~�ƎO���R�I�v�x�i���Y�t�H�A2020�N�j���B���Ғ��E�ďC�����B
�È�R�g�_�\���w�̏Ռ���
�����ƒ��ρ\��݂����鍡���юi
����簁@�����ɂ���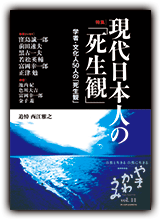
��� ���� ����
vol.11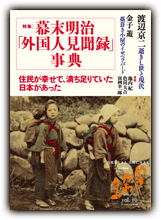
��� ���� ����
vol.10
��� ���� ����
vol.10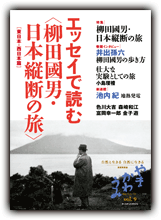
��� ���� ����
vol.9
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8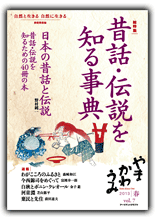
��� ���� ����
2013.�t�@vol.7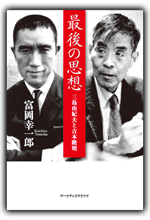
�Ō�̎v�z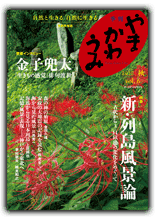
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6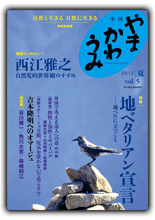
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5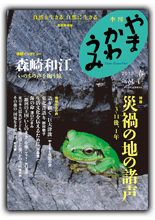
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4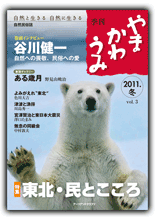
��� ���� ����
2011.�~�@vol.3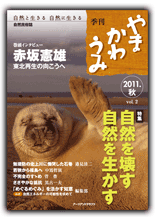
��� ���� ����
2011.�H�@vol.2
��� ���� ����
�n����2011.��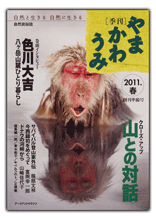
��� ���� ����
�n��������2011.�t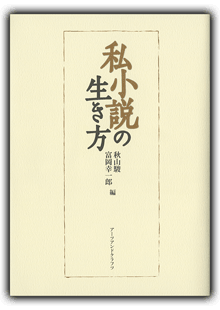
�������̐�����
����![���|�]�_�W](../../img/book/shadow/book_030.gif)
���|�]�_�W
�ȍs�F
-
�m�t �����i�ɂЂ�E�����܁j �@1969�N�A��錧�����s���܂�B1976�N����84�N�A���w1�N���璆�w3�N�܂Ŗ�9�N�ԃ��{�������B�����A83�N�̉Ăɒ��w2�N�ŃA�����J�ւ�1�����z�[���X�e�C�ɎQ���B�������ˈꍂ���B1988�N�A��q��w���w���N�w�Ȃɓ��w�̂��ߏ㋞������A����ɟT�Ǐ���x�w�A���ł̐��N�ɂ킽�鋏���Ȃǂ̂̂���w��ފw�A�A���o�C�g�ŌЌ������̂����X�𑗂�B1997�N�A27�̂Ƃ��A�s���ŕ�炵�Ă����A�p�[�g�̗אl�Ƃ̉�����\�t�g�E�F�A�J����Ђł���y���M���V�X�e��������Ђɓ��ЁB2006�N�A36�Ύ��ɉ�Ђ̌o�c�������p���A�����ɉ�Ђ����Ύs�Ɉړ]�����u���̑n�Ɓv��}��B2015�N����͈�錧�S��̌����J���^��Ɩ�30�Ђ̘A���̂ł����ʎВc�@�l�̑�\�����������B2019�N�ɂ͎Y�Ƃ̔��W�ɍv������Ƃ��Ĉ�錧�\������܁B
�������ł͒J��匤����E��؍F�v������ɂ����Ĕ��N�l�E���b�l�̈�l�Ƃ��ĉ^�c�⍲�����A�J�����������A�܂���؍F�v��撊P�ɐڂ��Ȃ���w�ԁB��̓Ǐ���@��g�̉�i�����j�A�}�L�E��ؓǏ���i�����j�ɂ��Q�����A���r��ς�ł���B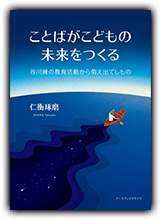
���Ƃ����ǂ��̖������������{�n���������i�ɂق߂����イ����j �@�n�������̗h�炮���A1981�N�A�����w�ҁE�J�쌒��̒̂��ƁA�u�n���͑�n�ɍ��܂ꂽ�l�Ԃ̉ߋ��̍����v�Ƃ̔F�������ƂɁA�w�ۓI�Ȓn�������̐i�W�A�n�������̍��g��ڎw���A���s�̋��͂̂��Ƒn�݂��ꂽ�B���N�A���X�ɉ������e�[�}���f���A��n�ɍ��܂ꂽ�n�����e�n�ɋ��߁A�S���n�������ґ���ςݏd�ˁA�u�n���v�́u�n���v�ł��邱�Ƃ��m�F���Ă����B
�@���݂����s�Ɍ�������u���A�@�֎��w�n���ƕ��y�x�A�𗬎��w���{�n���������ʐM�x�s���A���������̑b�Ƃ��A �ߔN�ł͂��g�߂ɒn����m��@��Ƃ��ĔN2��u�n���T�K�v�����{���Ă���B���㏊���E�J�쌒��A2�㏊���E�J�쏲�p�A�i���j�����E�֘a�F�i���{�Ñ�j�j�B
�Ñ�|�ߐ��u�n���v�����W�쑺 �h�q�i�̂ނ�E�������j �@1938�N���܂�B���{�@��{���b������ʼnP�c�r�ܘY�搶�Ɏw�����Č������|�̕����n�߂�B�쑺����ƌ�����͉ƒ�ɂ�����l�̍K�����l���Ȃ��猤���𑱂���B�e�[�}�͏����ƌ��B�u�o�Y�ƌ��v�̊ւ����w�^����̘̐b ���̑叕�x�Ō��B�̘b�����l�ɂ��Ắw���̉��L�\�\�������̌\�N�x�ɘ_�q�B�̋��̐^����Œ�ʒu�ώ@�𑱂��A�̘b�Œ������������H���ł���B 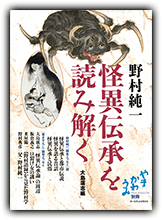
�쑺���� ���ٓ`����ǂ݉���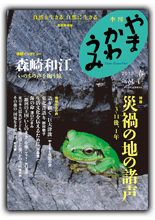
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4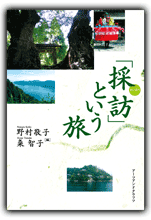
�u�̖K�v�Ƃ������쑺 ����i�̂ނ�E������j 1935�N�������܂�B���{�@��w�u�t�A���������o�āA1981�N�ɋ����ɂȂ�B2000�N4���Ɍ������Y�w�����̋Ɛт��̂����A�����J�͂���́B���w���m�B2007�N6��20���ɐ����B
����
�w�̘b�`���̌����x�i�����ɏo�Ł@1984�N�@��7��p�쌹�`�܁j
�w���{�̐��Ԙb�x�i�������Ё@1995�N�j
�w�]�˓����̉\�b�x�i��C�ُ��X�@2005�N�j
�w�̘b�̐X�x�i��C�ُ��X�@1998�N�j
�w���c���j���̑�̘b�ڍe�x�i���؏o�Ł@2002�N�@�Ғ��j
�w���{�`����n�x�S17���i�݂����ݏ��[�@1990�N�@���ҁ@��44���o�ŕ����܁j
�w�̘b�`�������T�x�i�݂����ݏ��[�@1987�N�@���ҁj
�w�����̘b�`���̌��݁x�i�א��Ё@1996�N�@���ҁj
�w���{���b�����T�x�i��C�ُ��X�@2002�N�@���ҁj�@�Ȃ�
�쑺����@���ٓ`���̐��E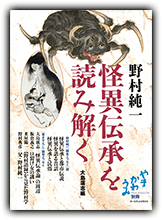
�쑺���� ���ٓ`����ǂ݉���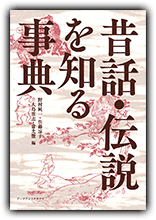
�̘b�E�`����m�鎖�T
�̘b�̗� ���̗�
�쑺����@�������|�̕����w
�͍s�F
-
���J�� �[�i�͂�����E�����j 1941�N�k�C�����܂�B1964�N�s�����ȑ�w���w�������ȑ��ƁA1976�N�@����w��w�@�l���Ȋw�����ȏC�m�ے��C���B1987�N�P�H�Ջ���w�������A1993�N�鐼�Z����w�����B���݁A���Z����w�q��������ސE���A�鐼���ۑ�w���u�t�B�����Ɂw������q�_�x�i�I���W���o�ŃZ���^�[�A1992�N�j�A���ďC�Ɂw�c���r�q�S�W�@�S10���x�i��܂ɏ��[�A2012�N�`�j�ȂǁB 
�t�F�~�j�Y���^�W�F���_�[��]�̌���
���㏗�����w��ǂ�
�R�W�����̌�����J�� �j�e�i�͂��ׁE�ӂ݂����j 1954�N�������܂�B���|�]�_�ƁB����c��w�@�w�����ƁB�w���Đ��������|��j�x�i�{�̎G���Ёj�ɂ���đ�46����{������Ƌ���܁i�]�_�E���̑��̕���j�A�w���{�~�X�e���[�i���_�x�i���{�o�ϐV���Ёj�ɂ���đ�8���O���w�����܁i�]�_�E��������j����܁B���̒����Ɂw�T�㏬���k�сx�i�Z���o�Łj�w���������Ɍ���Ï���x�i�}���o�ŎЁj�w�C�O�~�X�e���Ύ��L�x�i�u�k�Ёj�w���̍]�ː에���̌��x�w�C�O�~�X�e���V�����x�i�A�ϓ��o�Łj��������B 
�~�X�e���̕Ӌ���������R �āi�͂�����܁E�����j 1946�N�A�H�c�����܂�B���w�@��w��w�@���w�����ȁi���{���w��U�j���m�ے������ފw�B���ꍑ�ۑ�w�Z�啔�����ȋ������o�āA���݂͍O�O�w�@��w��w�@���w�����ȋ����A�����w�������B���m�i�����w�j�B�����Ɂw����̍��J�`���̌����\�V��E�_�́E���\�x�i���؏��[�A2006�N�j�A�w�͓������̎R�C�̐��\�͖�Ղƍ����t�\�x�i���n�ЁA2010�N�j�A�w�\���q�����r�̕����x�i�O�O�w�@�o�ʼn�A2015�N�j�A�w��؎R�̐_�ƋS�x�i�k���V�ЁA2016�N�j�B 
���t�̎��̔��z
���t�̎��ƐY�̔��z���� ����q�i�͂��Ƃ�E�܂����j �@ 
�������Y���N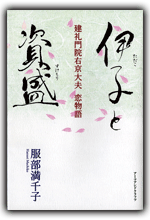
�Ɏq�Ǝ����� �G�F�i�͂₵�E�ЂłЂ��j 1934�N�������܂�B�w�K�@�����Ȃ��55�N�`61�N�A�ƃU�[����w�A�������v���G��w�Ɋw�ԁB�N�w��U�B�A����A���R�P�O�Ɏt�����A�e���r�E�f��̋r�{�ƂƂ��Ċ���B�u��������11�l�v�u��҂����v�u���l�̌Y���v�u���q�̊C�v�Ȃǂ̋r�{�̂ق��A�����ɏ����w�[�T�x�w�����邽�߂̏�M�Ƃ��Ă̎E�l�x�i�n�юЁj�A�]�_�w���{���̂ĂāA���{��m�����x�w�݂���̍\���x�i���v�Ёj�ȂǑ����B88�N���I�[�X�g�����A�ɈڏZ�B 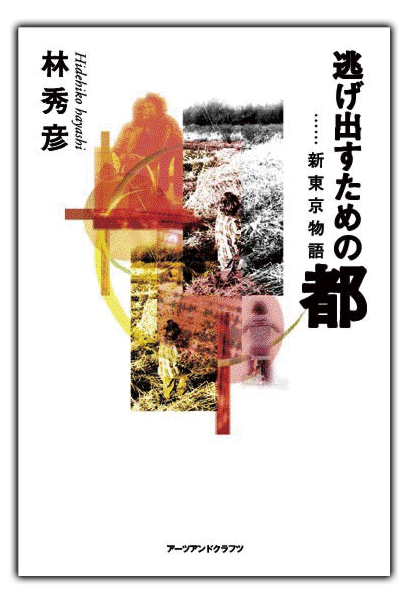
�����o�����߂̓s���{ �ߎq�i�Ђ������ƁE�����j ��ԑ����t�����[�f�U�C�i�[�B
�ԉi����ɁB�X�����܂�B�Ԃ�ʂ��āA���{�̐��_��`���قȂ镶���̒��a�E�Z����ڎw����������W�J�B�Ԃ���l���A������ꂽ�Ԃ��A���������l���A���ׂĂ����������u�ԉi�������@��������ԁv����A�����Ŏw�����邩�����A�p�[�e�B�E�Z�����j�[���̑��������̏���C�O�܂ōL���Ă���B���ɃC���e���A�E�A�[�g�̃f�U�C����u���������B
1998�N11���u���{�ߎq�̃t�����[�A�����W�����g�@�̎���v�i���ƔV���{�Ёj���o�ŁB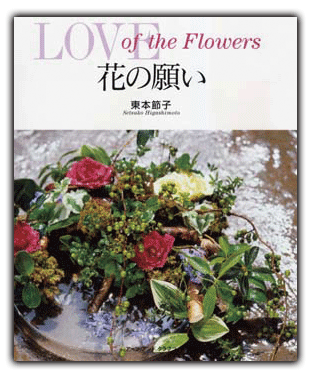
�Ԃ̊肢���c �q�Y�i�ӂ����E�Ƃ����j ����ƁA�쎌�ƁA���o�ƁB1928�N�A���s�s���܂�B��ˉ̌��c�A���c�l�G���o�āA��Ƃ��ă~���[�W�J���̐���i�r�{�A�쎌�A���o�j�Ɍg���A���{�̑n��~���[�W�J���̑������I���݁B�܂��A������ƂƂ��Ă̎d���������A1964�N�ɂ̓e���r�����̃I�[�P�X�g���ԑg�u�薼�̂Ȃ����y��v�𗧂��グ�A35�N�ɂ킽���Ċ��\����S���B1970�N�ɂ͉��o�ƂƂ��āu���E�̗w�Ձv�i���}�n���y�U����j�̑��ē��Ƃ߂��B
����
�Y�ȑI�W�w�����[�E�}�����[���x�i�b�̓��W�Ёj
�w�~���[�W�J���͂��D���H�x�iNHK�o�Łj
�w�V���N���[�h���y�̗��x�i�������y�����فj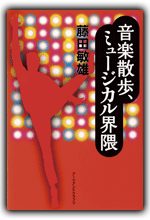
���y�U���A�~���[�W�J���E�G���{ �h�V���i�ӂ����ƁE�����̂����j ���a11�N�i1936�j�F�{���e�r�s�ɐ��܂��B���a35�N�i1960�j���s��w���w���Ȋw�����ƁB����������ш��L�@�ލH�Ƃ��o�āA���݁A�����b�v�������@�n��헪�������ɋΖ��B�o�R�ƁB���s��w�w�m�R�x��iAACK�j����B���{�����̍���̂قƂ�ǂ�o������яc���B���[���b�p�A���v�X�E�u���C�g�z�����i4176���j�A�A�������z�����i4087���j����у����u�����i4807���j�ȂǑ����̍���ɂ�������o�������B�J���`���b�J�����ō���N�����`�F�t�X�J���i4850���j�o�������������B
����
�u�킪����\��������ւ̗��v�i�z���Ё@2001�N�j
�u�ԗ�߂���v�i�z���Ё@2001�N�@�{���o�ŕ�����܁j
�u�y���Ȃ�N�����`�F�t�X�J���v�i�A�[�c�A���h�N���t�c�@2003�N�@NHK���W�I���i��B�n��j�ňꕔ�N�ǁj
�u���͂̌n���\�X���O�Ə��_�v�i2004�N�@���܂˕��w��܁@�S���}���ً���E�}���j
�u�lj��̓��X�v���o�̏ꏊ�v�i�����b�v�������@�n��헪�����@2005�N�j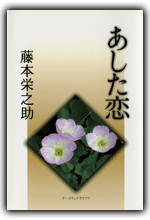
��������
ꡂ��Ȃ�N�����`�F�t�X�J������ �����i�ق��́E�ӂ݂����j 1946�N�A�D�y�s���܂�B����o�ϑ�w�ցB1971�N11���A����Ԋҋ����y�j�~�����ɎQ���B�u�E�l�߁v�Ŏw����z����A75�N�ߕ߁A�N�i�B��R��������20�N�A��R���������B�㍐���p�Ŗ����Y�m��B�Ŏq�ƍ��������B2019�N5���A�����{���l������ÃZ���^�[�Ŏ����B���N73�B 
���̍���̂ڂ��ā@���앶���E�Ŏq�@���������������� �Ŏq�i�ق��́E�������j 1954�N�A�R�`���đ�s���܂�B�R�`��w�݊w���ɔ���^���ɎQ���B1986�N9���A�����ƍ��������B�����Ɏ���W�wFumiAkiko�x�A�w������39�N�A���ǂ��������Ɗv���x�B2020�N2���A��Õ����ɂ�镶���̍����ɂ��č��̐ӔC��₤���Ɣ��������i�ׂ��i�B 
���̍���̂ڂ��ā@���앶���E�Ŏq�@�������������x�� �M�a�i�ق肤���E���������j 1960�N�A�������܂�B�����w���B�G���u�|�p�C�v�Ńt���[�G�f�B�^�[���o���������ƁA�G���u�쐫����v�ō�ƂƂ��ăf�r���[�B��Ȓ����ɁA�����w���C���n���g�ɉ�����x�w�D���������āx�w��Ԕ�s�x�w�ޏ��B�Ɖ߂��������ԁx�A�I�s�G�b�Z�C�w�A�E�g�E�I���E�U�E���[�h�x�ȂǁB�Ɂw���ӂ��l����ĂĂ��ꂽ�x�w�W���Y�E���C�t�x�ȂǑ����B 
�P�O�O�N�J�t�F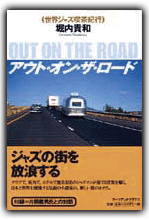
�A�E�g�E�I���E�U�E���[�h
�܍s�F
-
�O�c ���v�i�܂����E�͂₨�j 1944�N�A���䌧���܂�B���������ҁB������w�p�ĕ��w�ȑ��ƌ�A�V���Ђɓ��ЁA1995�N����2003�N�܂ŕ��|���u�V���v�̕ҏW���߂�B1987�N�ɔ��R�M�Ȃǂ̌�����ړI�Ɂu���R�̉�v�������B�����Ɂw�]�������@�e�r�R�Ƃ̐l�Ɗw��x�i�����ЁA�ǔ����w��܁j�A�w�يE����x�w���̖����w�ց@���R�M�̓��ǂ��āx�w�C�l���̌Ñ�j�x�i�͏o���[�V�Ёj�A�w�ÓT�V���@������ꂽ�ً�Ԃ�q�˂āx�i���}�Ёj�A�w�C��n�������R�M�x�i���㏑�فj�A�w�ӓy����x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�u�V�������v�̕S�N�q���҂̉��r�̐^���x�w�V�N�̓Ǐ��x�i�V���Ёj�A�w�J�쌒��ƒJ���@���_�̋��ɍR���āx�w�����̃��[�g�s�A�@�V���E�V�������̂��߂Ɂx�i�y�R�[�C���^�[�i�V���i���j�ȂǁB 
��l�ϐl�݂͂����҂��̂�����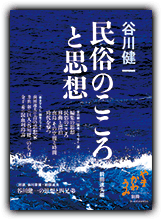
�J�쌒��
�����̂�����Ǝv�z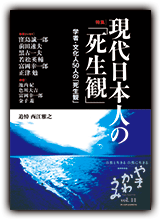
��� ���� ����
vol.11
�������� ���{�l�̋N����T�闷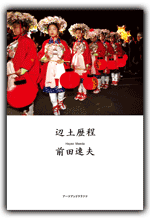
�ӓy����v�c �S��i�܂����E�䂤�����j 1955�N����c��w��ꕶ�w�����p�j�w�ȑ��ƁB���p�G���A���p���̕ҏW�҂��o�āA64�N�t�����X���{����Z�p���w���i66�N�A���j�B74�N���g�O���t�B�ʼn�H�[���A�g���GMMG�ݗ��B91�N�M�������[MMG�ݗ��B2007�N�A�M�������[MMG���U�B 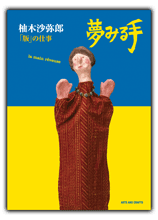
���݂���@
�s����������Y �����i�܂���E���݂��j �@ 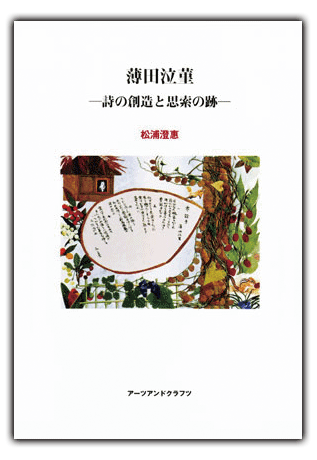
���c������Y ���i�܂���E�Ƃ���j 1931�N�A���m�s�o�g�B�_�ˑ�w���w�����B1977-78�N�A�I�N�X�t�H�[�h��w�q��������������w�@���ʌ������B85�N�A�w�p���m�iPh.D.�j�擾�B���݁A�����w���_�����i�C�M���X�ߑ㎍�A��r���w�j�B
��Ȓ����Ɂw�L�[�c�\���̖��ƌ����x�A�w���������̂͏�v�Ɂ\��係ƃL�[�c�̔�r���w�_�x�A�w�p������x�i��ȏ��[�j�A�w���̗d���̌n���\���w�ƊG����߂���يE�̕������x�i�����ЁA1995�j�A�w���̗���Ɂ\���Y�������Ê�L�O�_���W�x�i�������_���Əo�ŁA2000�j�A�ҖɁw�L�[�c�̎莆�x�i��ȏ��[�j�A�w�p��������ށx�w�p���̊��сx�i���}�Ѓ��C�u�����[�j�A�Ғ��Ɂw�p���Ɖf��x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�f��ʼnp������x�i���}�Ѓ��C�u�����[�j�ȂǑ����B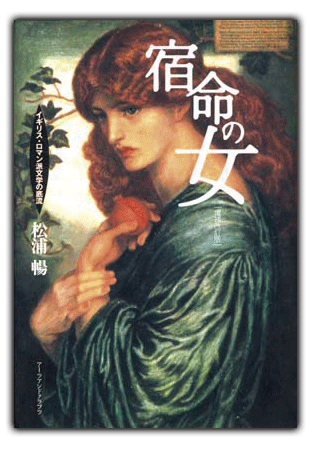
�h���̏�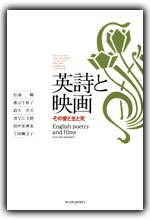
�p���Ɖf�����{ �P�v�i�܂��ƁE�Ă邨�j �@1943�N�A�ΐ쌧���܂�B������w���w�������ȑ��B�݊w���ɒ}�L�ŒJ���Əo��A69�N�A�J���̃e�b�N�i���{�j�ɓ��ЁB81�N�܂ł́A�d���̖T��J���g�������ɏ]���B�Ȍド�{����Z���^�[�{�����A�햱�����o�āA���Z���^�[��B�ގЌ�A2009�N�J��匤������N�����A�@�֎��u�_��v�s�B�܂�2010�N�t����؍F�v��������N������\�߂�B��Ȓ���Ɂw�J���@�i�v�H��҂̌���x�i���}�АV���j��_�l�u�ۓc�o�d�Y�o���v�i�L�����w���{�Q���h�x�����j�A�u��؍F�v�_�v�i�y�R�[�C���^�[�i�V���i���w��؍F�v�̐��E�x�����j�ȂǁB�ߔN�͉��ꔭ�̋G�����w���x�ɒJ���֘A�̘_�l�𑽐����\�B 
�q�����̑̌n�r���߂����ā@�J���@���{���n���̌������� �ׁi�݂����݁E�Ƃށj 1919�N3���A���䌧��ьS�{�����i�����������j�ɐ��܂��B�����ّ�w���w�����ށB���A�F��_��Ɏt���B������w�t���C�p���̉́x�i1948�N�A�����Ёj���x�X�g�Z���[�ɂȂ�B���̌�A���M�������牓�����邪�A1959�N�ɍĊJ�B�w��̎��x�i���Y�t�H�j�ő�45�؏܂���܁B�w���Ɖe�x�w�C�̉�x�w��⌶�z�x�i�͏o���[�V�Ёj�A�w�Q��C���x�i�����V���Ёj�A�w�z�O�|�l�`�x�w��x�x�w�NJ��x�i�������_�Ёj�A�w�ܔԒ��[���O�x�i���Y�t�H�j�A�w�É͍͗�̐��U�x�i���}�Ёj�A�w�͂Ȃ��ڏ������x�i�V���Ёj�A�w�����x�i�}�����[�j�A�w�~�̌��i�x�i�����V���Ёj�������B2004�N9���i���B 
�ዷ������@�킪�u�����v�
�ዷ������U�@�킪�u�����v�
�������܂���m�T�̐������n���c �@�q�i�݂����E�̂肱�j 1937�N�����s���܂�B�������q��w�݊w���Ɂw���g�D�x�i�Ԃ��߂�̉�j�ɎQ���B1961�N�ɃC�F�[����w�ɗ��w�A���m���擾�B1983�N�܂ŕč���w�Ŕ�r���w�̋��ڂ��Ƃ�B�|�I�A�ߌ��㎍�A�����\���A��]���_�𒆐S�ɔ�]��W�J�B�ߒ��Ɂw���_�j�Y���Ɛ�㏗�����̓W�J�x�i�v���ЁA2012�N�j�A�w���݂Ȏq�@�L���̕��w�i���}�ЁA2013�N�j�A�w����ꕶ�ɐ��c�@�q���W�x�i���Ɏ��W�A�v���ЁA2016�N�j�B�鐼��w�w�����o�āA����w�O�������B�w�J�������ʂ�x���l�B2011�N�n���K���[���a�������M�́A2013�N�n���K���[���\���M�͎�́B2013�N���ێ��܁A�`�J�_��܁B 
�t�F�~�j�Y���^�W�F���_�[��]�̌���
���㏗�����w��ǂ�
�R�W�����̌���O�� ���q�i�݂₯�E���悱�j �@1939�N�É������܂�B������w�@�w���@���w�ȑ��B���l�ݏZ�B�����Ɂw�q��Ă̐X�̒��Łx�i�J���o�ώЁj�w����̍����a�@�̉��x�i����ݏo�Łj�w�Ƃ肱�ɂȂ�{�x�i�A�[�c�A���h�N���t�c�j�w�Đ��H�[�ւ悤�����I�x�i�邵�̎蒟�Ёj�A�����Ɂw�w�l��莫�T�x�i�w�K�̗F�Ёj�S�Ȏ��T�wNAVIX�x�i�u�k�Ёj�ȂǁB 
�Ƃ肱�ɂȂ�{2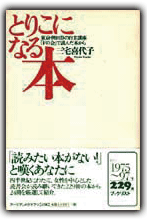
�Ƃ肱�ɂȂ�{�{�c �o�i�݂₽�E�̂ڂ�j �_�ސ쌧���l�s���܂�B1960�N�i���a35�j���������w���w�����ƁB����w�@���w�����Ȕ��m�ے��P�ʎ擾�ފw�B1976�N�i���a51�j�A�u�~���N�M�̌����F���{�ɂ�����`���I���V�A�ρv�œ��������w���w���m�B���������w����A�����w�|��w�������A�}�g��w���j�l�ފw�n�������A���������o�āA�ފ���ɐ_�ސ��w�o�ϊw�������B�������j���������ًq�������A�������������ی�R�c����ψ��ȂǁB2000�N�i����12�j2��10���A�̋@�\�s�S�̂��ߎ����B���]�l�ʁA�M�O������͒Ǒ��B 
�{�c�o�@�����I���j�_���������� �F���i�ނ�܂E�Ƃ��݁j 1940�N�A�����ɐ��܂��B�c��`�m��w���w�����ƁB�o�ŎЋΖ����o�āA���M�����ɓ���B1982�N�w���㉮�̏��[�x�ő�87�؏܂���܁B1997�N�w���q�̂�����x�ő�25��ԏ܂���܁B�����̏o����₤��i��l���̕]�`�I�ȍ�i�͓I�ɔ��\���Ă���B 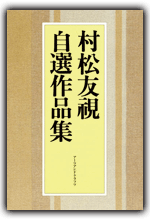
�����F�� ���I��i�W�X�� �r�Y�i���肤���E�Ƃ����j 1936�N��㐶�܂�B����c��w���w���I���ȑ��Ɓi�{�����v�A�������͓������j�B���|���o�Łu�~���Ёv�ŕҏW���߁A69�N�w�c���҂�醔n�ɏ���āx�ŕ��{�E�V�l�܁B69�`72�N�܂ŊH��܌��B73�N�Ɂw�Ăԉe�x�ő�1��ԕ��w�܁B75�`76�N���{�E�V�l�ܑI�l�ψ��B86�N�w���̉x���i���Y�t�H�A2004�N�u�k�Е��|���Ɋ��j�B91�N�w�X�͂�����܂łɁx�ǔ����w�܁E�|�p�I����܁B2016�N�����������w�����قŁq�X���r�Y�Ɠ����W�r�J�ÁB2017�N�Ɂw���̌������̓��x�i�V���Ёj�����s�B 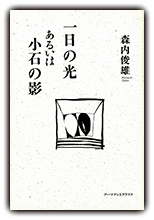
����̌����邢�͏��̉e�X�� �a�]�i���肳���E�������j �@1927 �N�A���N��緐��܂�B44 �N�A�����������q���w�Z�i���E�������q��w�j���w�B47 �N���ƌ�A���j�ō���×{���ɓ����B49 �N�A�ێR�L��ɂ́w�ꉹ�x�̓��l�ƂȂ莍�\�B58 �N�A���p�M�A�J����ƂƂ��ɕ����^�����w�T�[�N�����x��n���B59 �N�A�����𗬎��w�����ʐM�x��n���B60 �N�A�J��傪�g�D�����吳�s�����ɎQ���B63�N�A�Δn�֎�ށA68�N�A������Ċ؍��E�c�B�ցB���̌�A70�`80 �N��́A�����e�n����ނ���B60 �N�㖖��胉�W�I�h���}�𑽂���|����B���������B 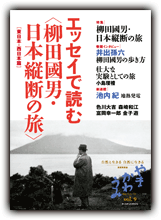
��� ���� ����
vol.9
���̂��̎��R
��� ���� ����
2013.�H�@vol.8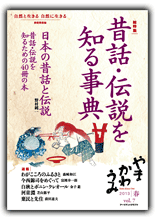
��� ���� ����
2013.�t�@vol.7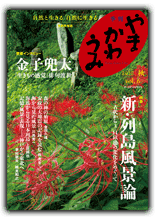
��� ���� ����
2012.�H�@vol.6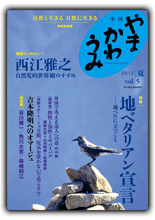
��� ���� ����
2012.�ā@vol.5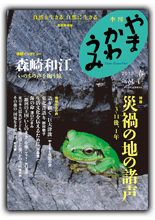
��� ���� ����
2012.�t�@vol.4
��s�F
-
�R�{ �����i��܂��ƁE���݂悵�j 1934�N�a�̎R�����܂�B����c��w��w�@�����ȏC���B��Ȓ����Ɂw�]�˂̉Ύ��ƉΏ��x�w�]�˓����̒n�k�ƉΎ��x�w�n�c��̗��j�x�w�s�����ڂ�Ȏj�x�A�����Ɂw����ƍN�Ɛb�c���T�x�w�������]�ː؊G�}����x�ȂǁB ![�]�ˁE���� ���������](../../img/book/shadow/book_010.gif)
�]�ˁE���� ����������M�� ����Y�i��̂��E���݂낤�j �@1922�N�A�������܂�B42�N�A����ɓ��w��A�w�k�o�w�B����46�N�A�匴���p�ًΖ����Ɂq���|�r�ɏo��B47�N�A�ڑ��C��Ɏt���A49�N�A�͂��߂đ�23���W�ɏo�i�B58�N�A�u�����b�Z������������œ��܁B72�N�A���q���p��w�����A87�N�A���q���p��w�w���B98�N�A�p��SAGA�W�A2003�N�A�����X�^���v�W�J�ÁB 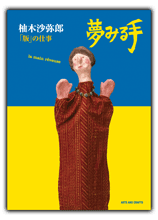
���݂������ ��q�i�悱���E�܂����j ���y�����ƁB���݁A�������y��w���y�w�����y�����f�U�C���w�ȏ������B�����Y�p��w�C�m�ے��C���B�������Ȍ������w���Ƃ��ăn���K���[�����Ȋw�A�J�f�~�[���y�w�������ɗ��w�B�n���K���[�A�X�����@�L�A�A���[�}�j�A�ȂǂŒ����E�������s���B�����̉��y�����A���y�����𒆐S�Ɍ����B��Ȓ����ɁA�w���y�ł߂��钆�����[���b�p�x�i�O�ȓ��j�A�w�}�W���[�����̂����@�o���g�[�N�̈������̐��x�i���{�r�N�^�[�j�A�w�������y�T�_�x�i���S���M�A�������Ёj�A�V���[���V�w�n���K���[�̉��y�@���̓`���ƌ�@�x�i�|��A���y�V�F�Ёj�ȂǁB 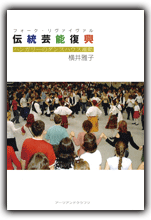
�`���|�\�����g�� �����i�悵�́E�Ђ�݁j 1959�N�A���������܂�B�F�{��w����w���S���w�ȑ��ƁB���������w�Z���@�B���݁A���p��]�ƂƂ��Ċ���B2004�N�A���p���D�ƒc�́EArtCollectorsOrganization�iACO�j�ݗ��B�N2��A����s�B 2007�N�A�w�ɓ��v�O�Y�\�n���̋O�Ղƌ|�p�ρx���|�Ђ��o�ŁB 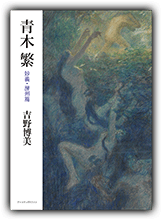
�ؔɁ@���`�E�[�B��
��s�F
-
�����i��E��イ�j 1937�`2020�N�B�Γ�ȌV�z�l�B������w�l���Љ�Ȋw���[�����B2012�N�A�����@�w����u�S�����o���[�@�w�Ɓv�ɑI�o�A2018�N�ɂ́u�Ζk�������l�v�A�u�t�^�ЉȖ��Ɓv�ɑI���B����܂łɍ��ۖ@�N�w�ƎЉ�N�w����������A�����@�w��w�p�ψ���ψ��A�����@�w��햱�����A�����@�w��@���������E�ږ�Ȃǂ��C�B��Ȍ�������͖@���w�A���@�w�A�@�w����B�����⋳�ނ�40���]��B�w�����Љ�Ȋw�x�A�w�V�ؕ��E�x�A�w�@�w�����x�A�w�����@�w�x�ȂNJj�S�I�w�p����200�]��̘_�����f�ځB�����ɂ́w���@��b���_�x�A�w�@���w�x�i2002�N�j�A�w�˖@�����������{��茤���x�i2004�N�j�A�w�l�{�@���ό����x�i2009�N�j�ȂǁB 
�����@���w���W�j
-
�C�q���i��E���������j 1969�N���܂�B�ؒ��t�͑�w�y�����B�E�_���Ɂw���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n�ʁx�i����A�A�[�c�A���h�N���t�c�j�A�w�@���Љ�ɂ������{�I�l���\���W���̖@�I���x�����x�i�A����Ёj�A�w���S�_�������i����l���E���s�ޑ�l���j�x�i����A�����Љ�Ȋw�o�ŎЁj�A�u�w������x���`�����I�F�m���́v�i�w�ꕶ�����w���i�n�����j�x�A�u���w���\�ʁx�Ґ��w�v���X�̃G�l���M�[�x�H�\�_�|������I�I���v�i�w�V���I�p��y�V������I�T���a���W�x�j�ȂǁB 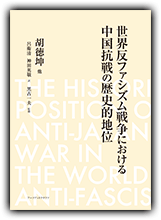
���E���t�@�V�Y���푈�ɂ����钆���R��̗��j�I�n��
�����@���w���W�j
��s�F
-
�� �C���i�����E�n�C�����j �@1974�N9���@�����R���Ȑ��܂�B
�@1997�N7���@�R���t�͑�w���w�������ꒆ�����w��U���ƁB
�@1997�N8���`2003�N8���@�R���Ȍ|�p�w�Z�������o�āA�R���|�p�w�@�u�t�B
�@2003�N9���@�}�g��w�}���ُ�f�B�A�����Ȃ̌������Ƃ��ė����B
�@2007�N3���@�}�g��w�}���ُ�f�B�A�����Ȕ��m�O���ے��C���A�C�m�擾�B
�@2011�N4���@�������Ȕ��m����ے��C���A�w�p���m�擾�B
�@���݁A���U��w�������ꕶ�w�n�u��r���w�Ɛ��E���w�v�������|�X�E�h�N�B
�@�{���̊�ɂȂ������m�_���u����t���ƒ����`�����ɂ����鑺��t���̎�e�����𒆐S�Ɂ`�v�̂ق��A�u�����ɂ����鑺��t���̎�e�v�i���È�v���w����t���u�r���v�̕��ꂩ��u�]���v�̕���ցx2007�N10���A�א��o�Ŋ������j�ق��A�_�������B
����t���ƒ���
